暗号資産の利益は事業所得?雑所得?確定申告の基本から事業所得の条件、メリットまで徹底解説
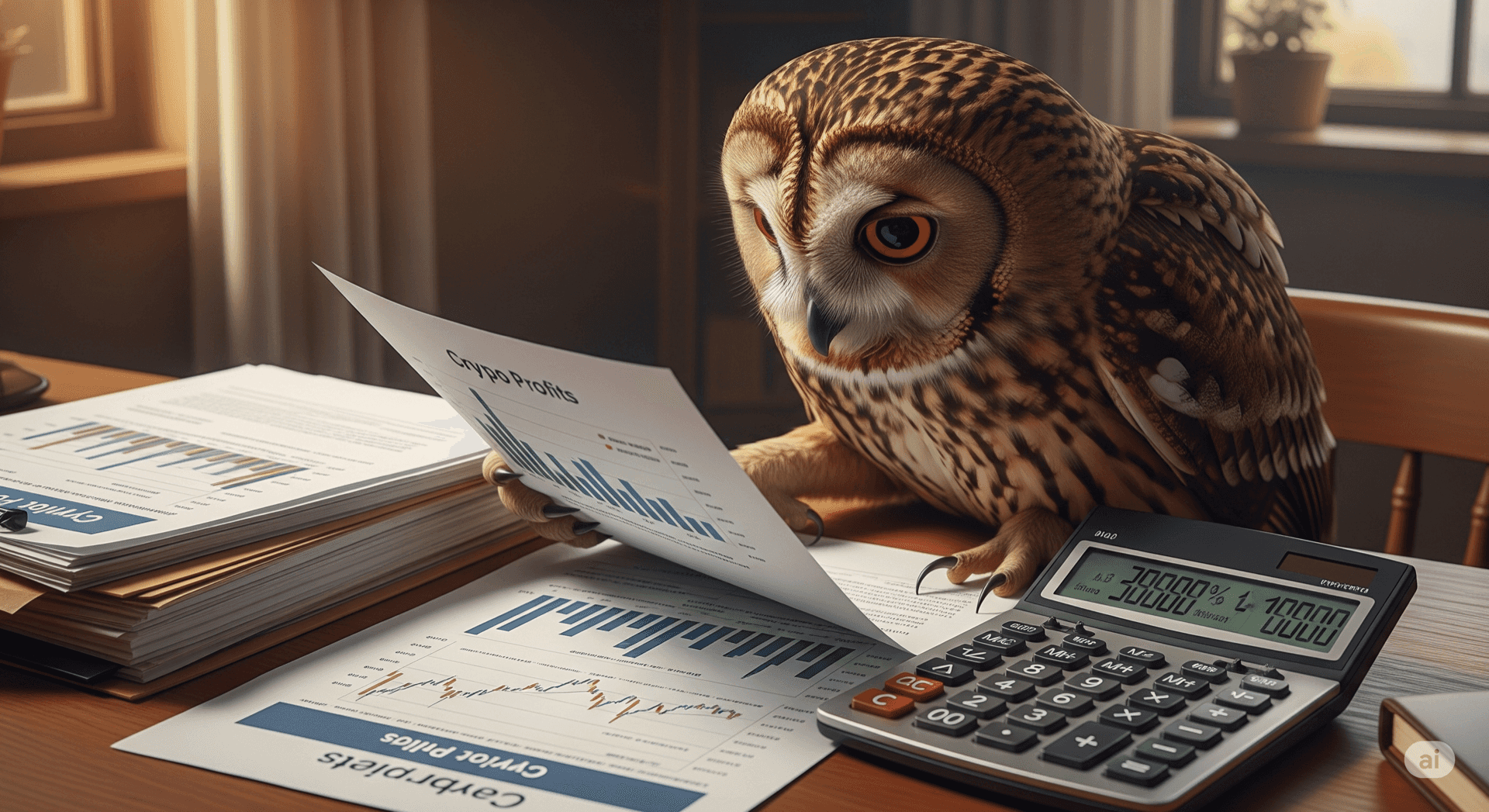
暗号資産(仮想通貨)の取引で得た利益を確定申告する際、その所得が「事業所得」として認められるのか、それとも「雑所得」として申告すべきなのかは、多くの投資家が直面する重要な問題です。所得区分によって納税額が大きく変わる可能性があるため、その違いを正確に理解することが不可欠です。
この記事では、国税庁の公式見解や過去の判例を基に、暗号資産の利益に関する税務上の基本的な考え方から、事業所得として申告するための具体的な要件、とくに注目される「300万円基準」の正しい解釈、そして事業所得で申告することのメリットとデメリットに至るまで、専門的な観点から徹底的に解説します。
目次を表示
暗号資産(仮想通貨)の利益にかかる税金の基本₿
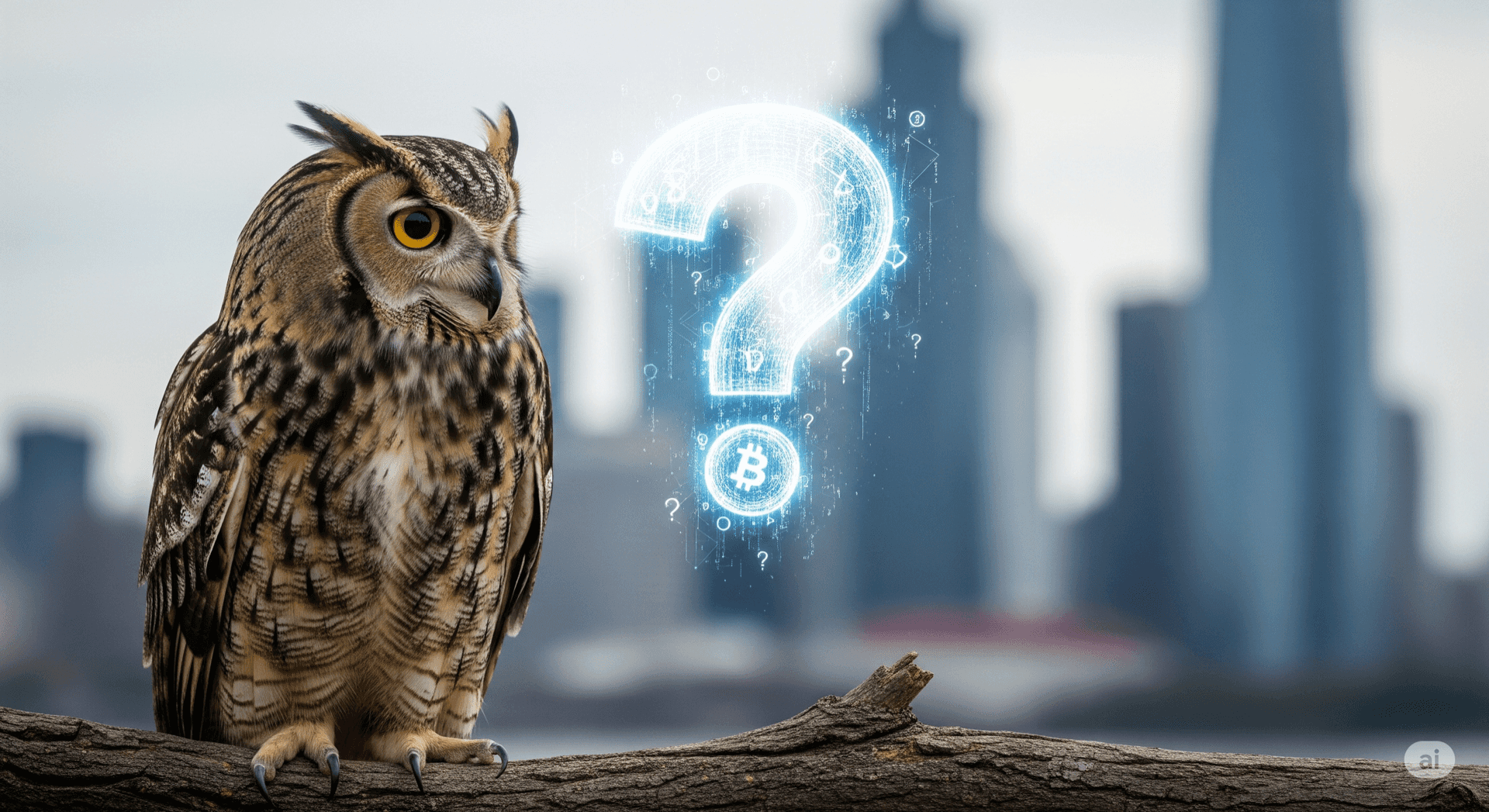
まず、暗号資産の利益に対する課税の基本的な仕組みを理解することが、適切な申告への第一歩となります。原則的な所得区分とその理由、具体的な税額計算の方法について解説します。
- 原則は「雑所得」。なぜ事業所得ではないのか?
- 雑所得の場合の税金の計算方法と税率
- 具体例:暗号資産で100万円の利益が出たら税金はいくら?
原則は「雑所得」。なぜ事業所得ではないのか?₿
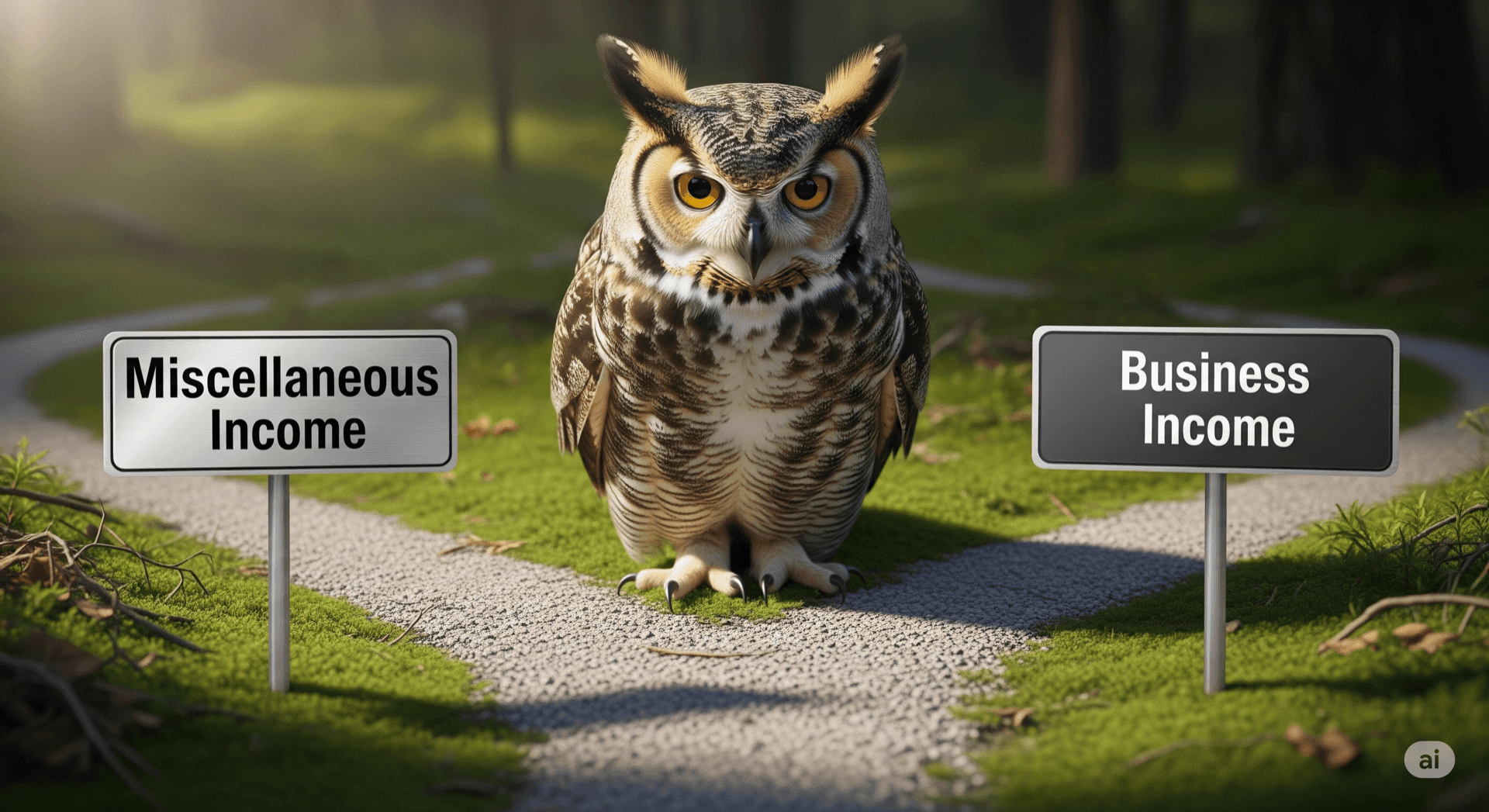
国税庁は、個人が暗号資産の売買や使用によって得た利益について、原則として「雑所得」に区分されるという見解を一貫して示しています。所得税法では、所得を利子所得、給与所得、事業所得など10種類に分類していますが、雑所得は他の9種類のいずれにも該当しない所得を包括する区分とされています。
多くの個人投資家による暗号資産取引は、生計を立てるための継続的・反復的な「事業」とまではいえず、資産運用の一環と見なされるため、この雑所得に分類されるのが一般的です。ただし、既存の事業における決済手段として暗号資産を使用した場合など、事業に付随して生じた利益は事業所得に含まれることがあります。また、取引の規模や態様が社会通念上「事業」と認められる水準に達している場合は、事業所得として申告できる可能性も残されています。
この「雑所得」という初期分類は、単なる事務的なラベル付けではありません。この分類によって、適用される税率の計算方法、損失が出た場合の取り扱い、利用できる控除の種類など、納税額に直結するすべての税務ルールが決定されるため、極めて重要な意味を持ちます。
雑所得の場合の税金の計算方法と税率₿
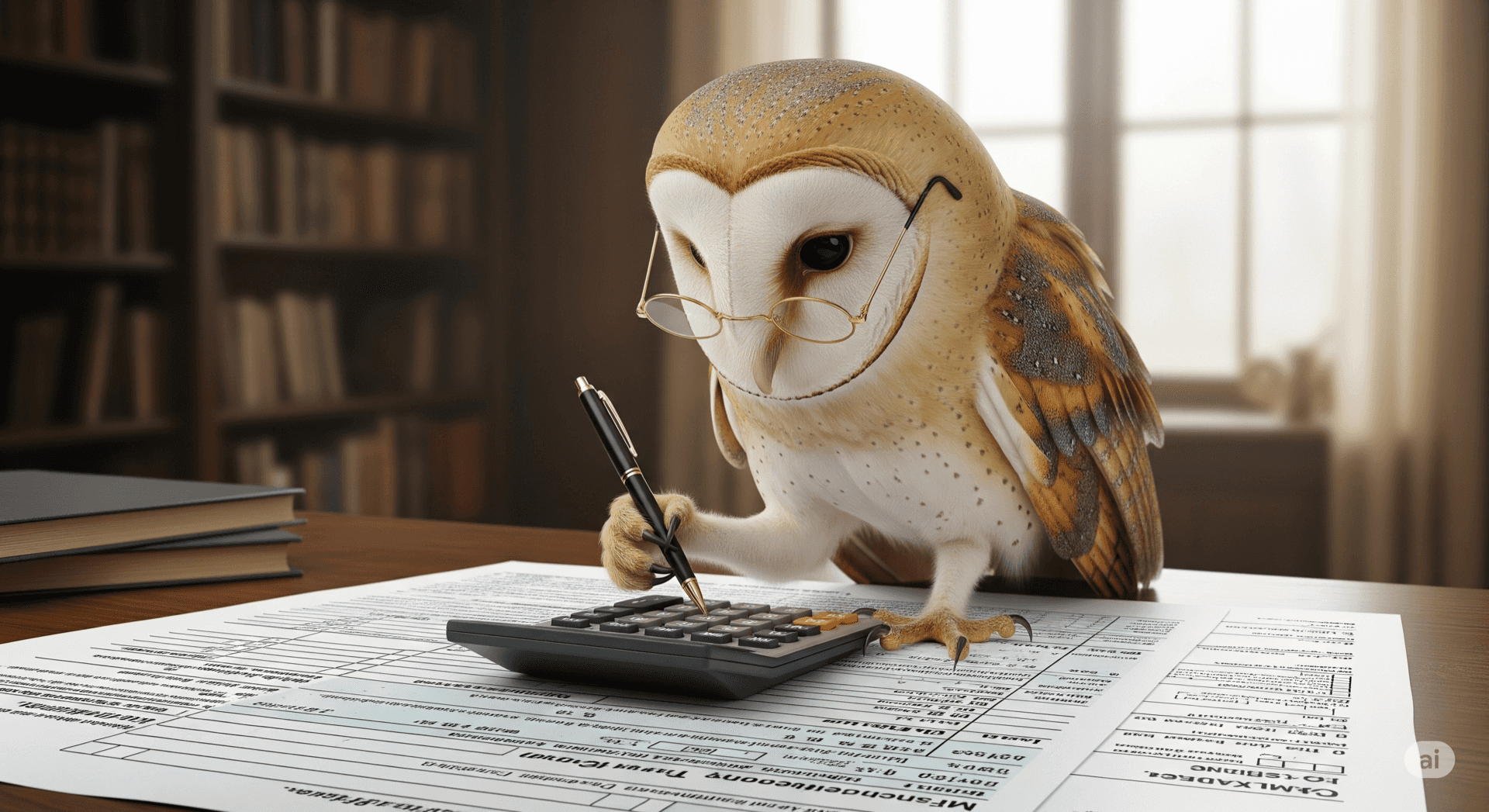
暗号資産の利益が雑所得に区分される場合、その税額計算には「総合課税」という方式が適用されます。これは、暗号資産から得た所得を、給与所得やその他の雑所得(例:副業の原稿料など)といった他の所得と合算し、その合計金額に対して税率を掛けて所得税額を算出する方法です。
日本における所得税は、所得が大きくなるほど高い税率が適用される「累進課税」制度を採用しています。税率は5%から45%までの7段階に分かれており、これに一律10%の住民税が加わります。したがって、合計の税率は最大で約55%に達する可能性があります。
表1: 所得税の速算表(令和5年分以降)
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
参考:No.2260 所得税の税率|国税庁
この表を用いて、所得税額は次の式で計算されます。
所得税額=課税所得金額×税率−控除額
具体例:暗号資産で100万円の利益が出たら税金はいくら?₿
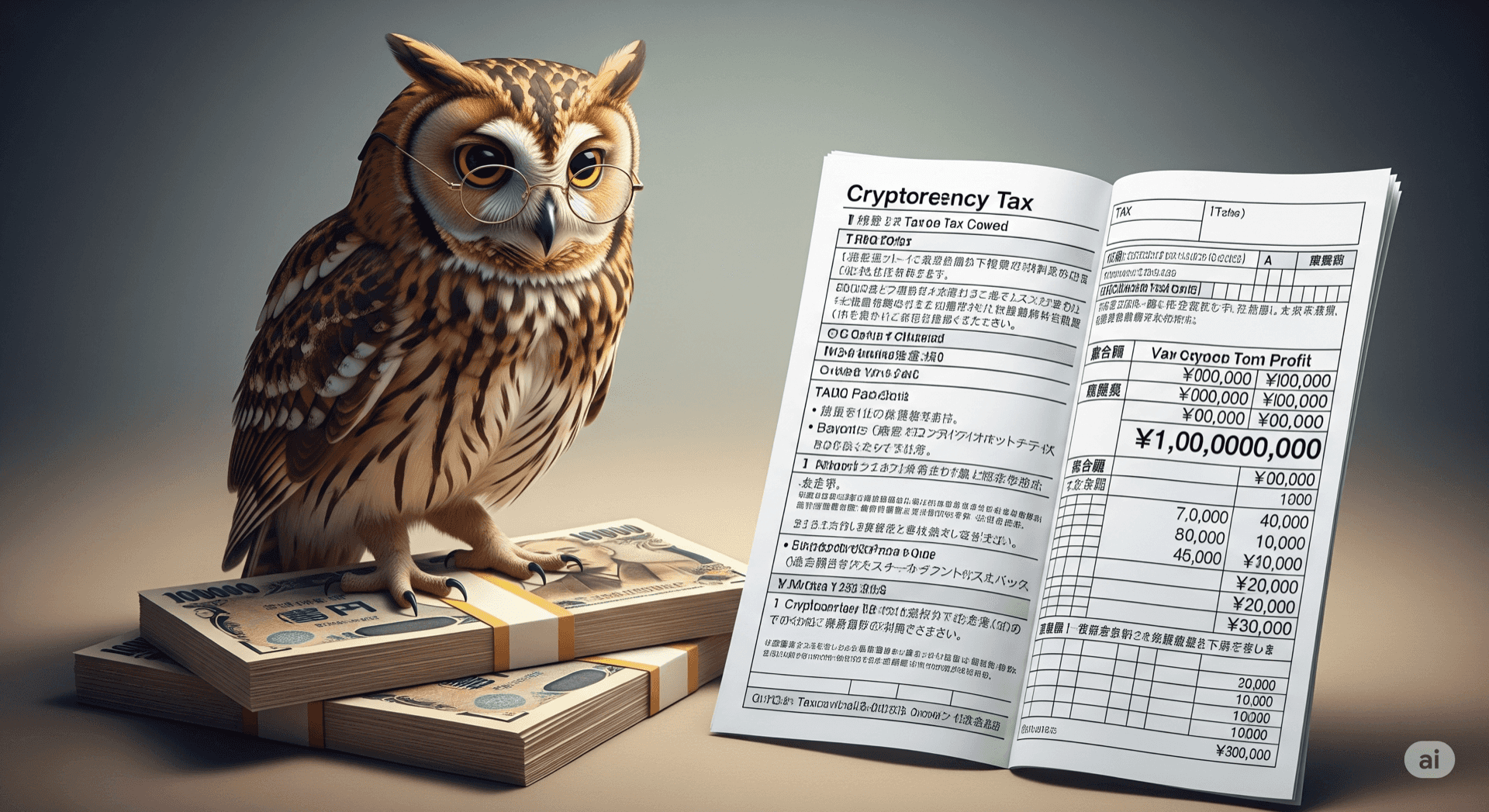
同じ100万円の利益でも、他に所得があるかどうかで税負担は大きく異なります。総合課税の仕組みを理解するために、2つのケースで税額をシミュレーションします。
シナリオA:年収500万円のサラリーマンの場合
給与所得がある会社員が副業として暗号資産取引を行い、100万円の利益(経費等を差し引いた所得)を得たケースです。この100万円は給与所得に上乗せされて課税対象となります。
年収500万円の場合、給与所得控除などを適用した後の課税所得は約250万円から300万円程度になります。ここに暗号資産の利益100万円が加わることで、合計の課税所得は350万円から400万円程度となり、適用される所得税率が10%から20%へと上昇します。結果として、100万円の利益に対して追加でかかる所得税と住民税の合計額は、約20万円から30万円程度になることが見込まれます。
シナリオB:他に所得がない個人事業主(または専業トレーダー)の場合
暗号資産取引のみで生計を立てており、年間の利益が100万円だったケースです。この場合、課税所得は100万円から基礎控除(48万円)などを差し引いた金額になります。
課税所得が52万円(100万円 - 48万円)だとすると、適用される所得税率はもっとも低い5%です。
このケースでは、所得税と住民税を合わせても、税負担はサラリーマンのケースより大幅に低くなります。このように、総合課税では他の所得の有無が税額に直接影響を与えるのです。
暗号資産の利益を「事業所得」として申告するための条件とメリット₿

雑所得に比べて税制上有利な点が多いことから、多くのトレーダーが事業所得での申告を目指します。ここでは、そのメリットと、認められるための厳しい条件について掘り下げていきます。
- なぜ事業所得を目指すのか?雑所得との違いと大きなメリット
- 事業所得として認められるための客観的な判断基準
- 【重要】令和4年分以降の「事業所得300万円基準」を正しく理解する
- 過去の判例から見る、事業所得と判断されるポイント
- サラリーマン(給与所得者)でも事業所得として申告できる?
なぜ事業所得を目指すのか?雑所得との違いと大きなメリット₿
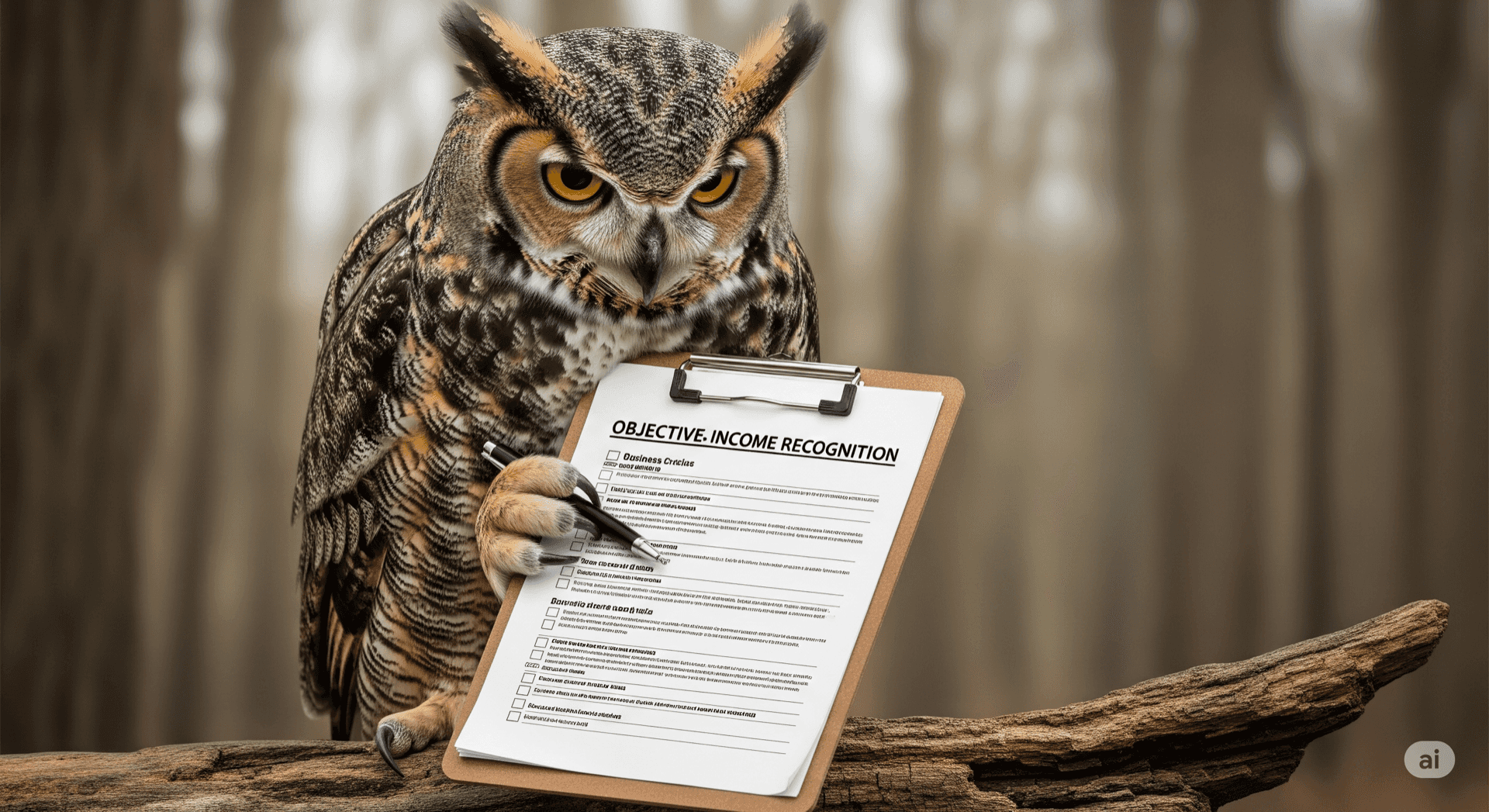
事業所得で申告することには、雑所得にはない3つの決定的な税制上のメリットがあります。これらを活用できるかどうかが、手元に残る利益を大きく左右します。
損益通算
事業所得の最大のメリットの1つです。暗号資産取引で損失(赤字)が出た場合、その損失額を給与所得や他の事業所得などの黒字から差し引くことができます。これにより、全体の所得が圧縮され、納めるべき税金が減額されます。一方、雑所得の場合、暗号資産取引でどれだけ大きな損失を出しても、給与所得など他の所得と相殺することは一切できません。
青色申告特別控除
事業所得者で、所定の手続きを経て「青色申告」を選択すると、所得金額から最大で65万円を控除できます。これは経費とは別に所得から直接差し引けるため、非常に節税効果が高い制度です。この控除を受けるには、複式簿記という正規の簿記原則に従った帳簿作成が求められます。
損失の3年間繰越控除
青色申告を行っている場合、損益通算をしてもなお残る純損失(赤字)を、翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。たとえば、ある年に300万円の損失を出し、翌年に500万円の利益が出た場合、前年の損失を差し引いて200万円の利益として申告できます。価格変動の激しい暗号資産市場において、年をまたいで損失と利益を平準化できるこの制度は、長期的な安定経営に不可欠です。雑所得では、その年の損失はその年限りで切り捨てられ、翌年に繰り越すことはできません。
表2: 事業所得と雑所得のメリット・デメリット比較
| 特徴 | 事業所得 | 雑所得 |
|---|
| 損益通算 | 可能(給与所得等と相殺可) | 不可(他の所得と相殺不可) |
| 損失の繰越控除 | 可能(青色申告の場合、3年間) | 不可 |
| 青色申告特別控除 | 可能(最大65万円) | 不可 |
| 経費の範囲 | 事業に関連する幅広い経費が認められやすい | 取引に直接要した費用に限定されやすい |
| 帳簿作成義務 | 必須(白色申告でも記帳・保存義務あり) | 必須ではない(ただし所得計算の根拠は必要) |
事業所得として認められるための客観的な判断基準₿
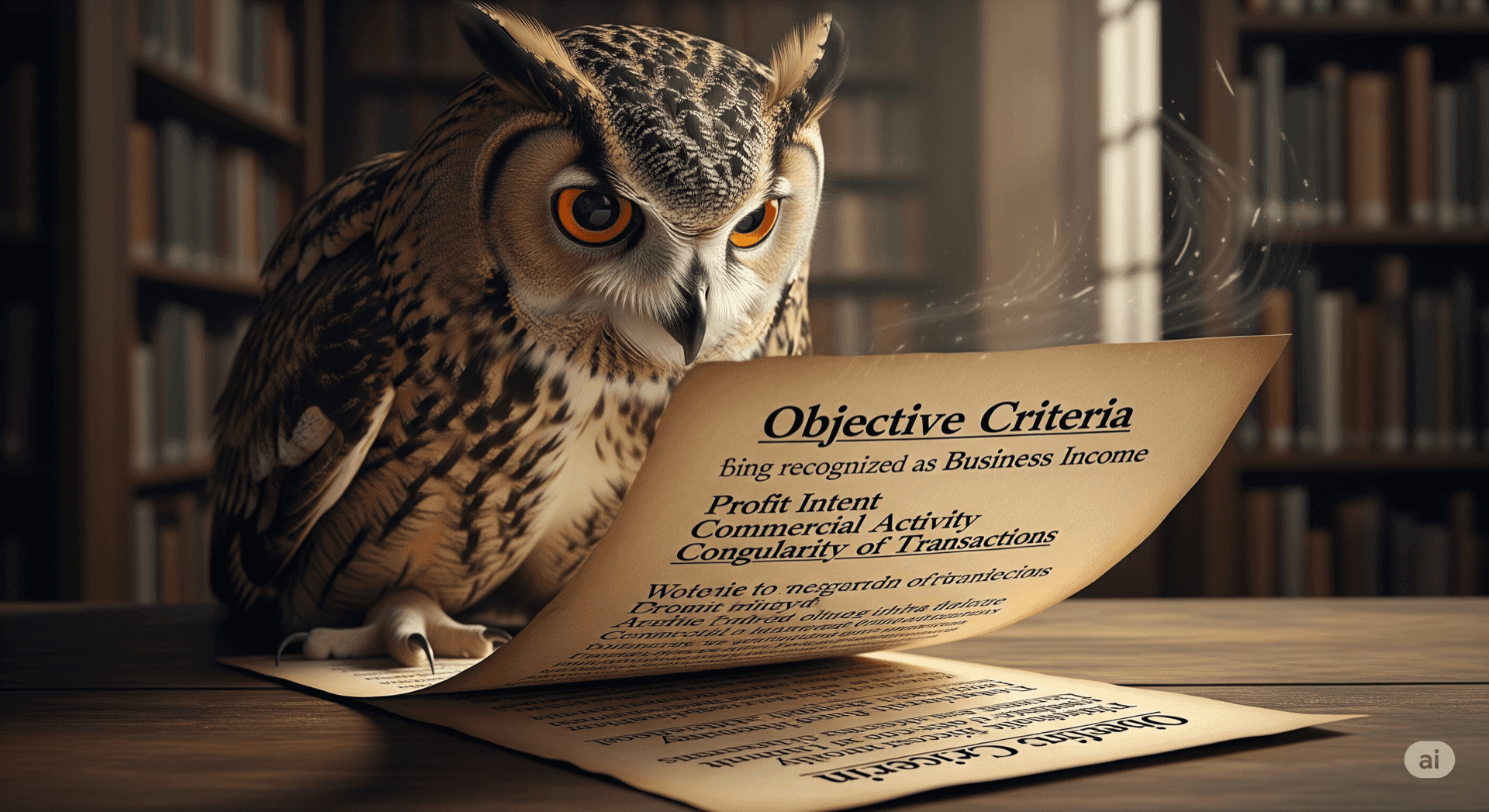
単に「これは事業だ」と主張するだけでは、税務署に事業所得として認められることはありません。過去の判例などでは、社会通念上「事業」と呼べるかどうかを判断するために、いくつかの客観的な基準が示されてきました。これらは、後述する「300万円基準」が導入された後も、事業性の本質を判断する上で依然として重要な要素です。
営利性・有償性: 明確に利益を得る目的で活動が行われていること。
継続性・反復性: 一時的な取引ではなく、継続的かつ反復的に取引が行われていること。
自己の計算と危険における企画遂行性: 他者からの指示ではなく、自己の判断と責任(リスク)において独立して事業を計画・実行していること。
費やした精神的・肉体的労力: 活動に費やされる時間や労力が、片手間の趣味のレベルを超えていること。
これらの要素を総合的に勘案し、その活動が安定した収入を得られる可能性を持ち、職業として成立しうる客観的な実態を備えているかどうかが問われます。
【重要】令和4年分以降の「事業所得300万円基準」を正しく理解する₿
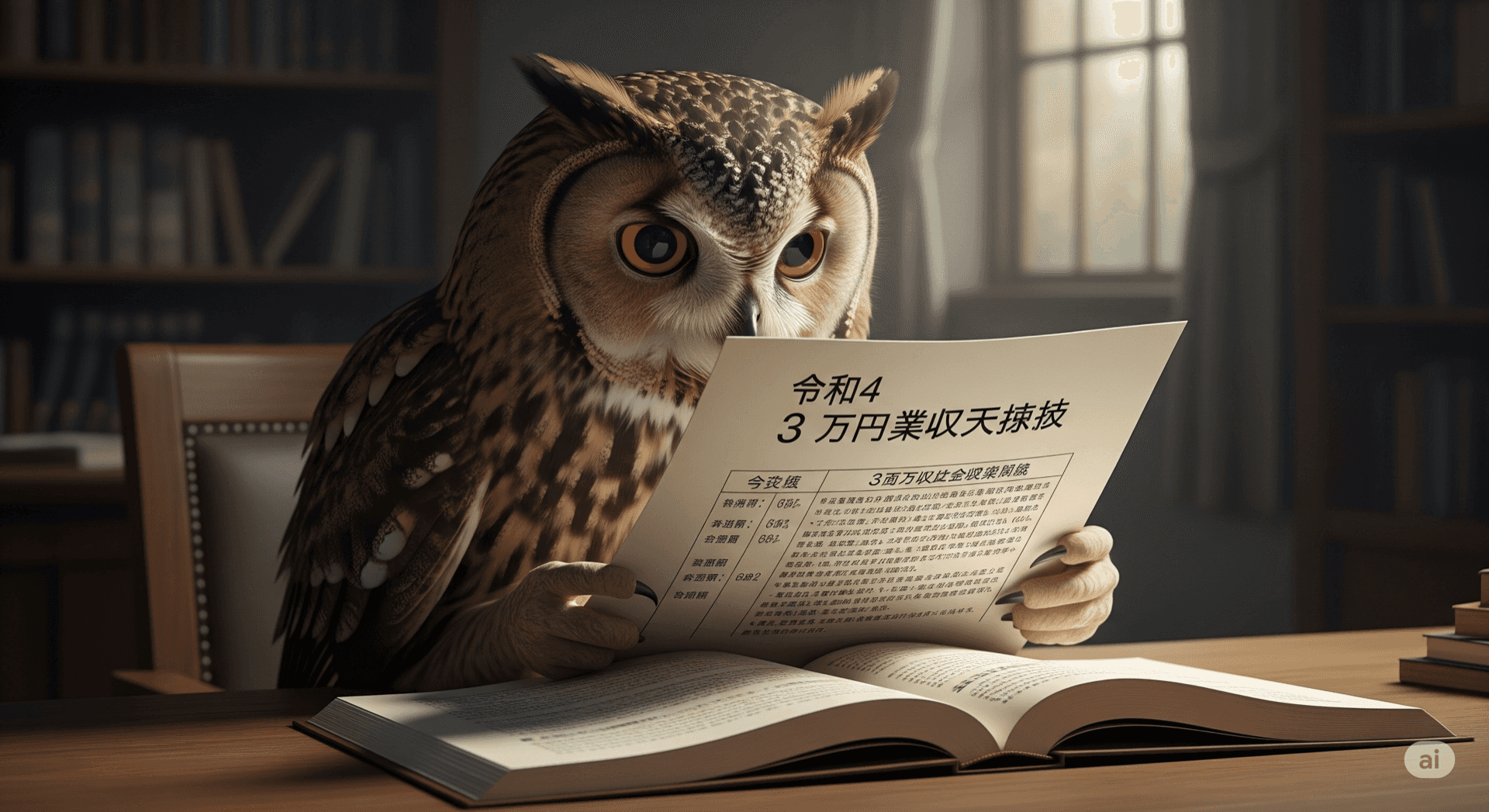
暗号資産の所得区分に関する不明確さを解消するため、国税庁は令和4年(2022年)12月に「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」を改訂し、新たな判断基準を公表しました。これが、いわゆる「300万円基準」です。
この基準の要点は以下の通りです。
原則: その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超え、かつ、その取引に関する帳簿書類の保存がある場合には、原則として「事業所得」に区分されます。
収入金額とは: ここでいう「収入金額」とは、売却益や所得(利益)ではなく、売却や交換によって得た金額の総額を指します。たとえば、400万円で購入したビットコインを500万円で売却した場合、利益は100万円ですが、収入金額は500万円となります。この点を誤解すると、判断を大きく見誤るため注意が必要です。
帳簿保存が前提: 300万円の収入があっても、取引を記録した帳簿を適切に作成・保存していなければ事業所得とは認められません。その場合、損益通算などができない「業務に係る雑所得」に区分されることになります。
300万円以下の場合: 収入金額が300万円以下であっても、直ちに事業所得が否定されるわけではありません。前述の社会通念上の基準に照らして、事業としての実態が客観的に認められれば、事業所得として申告できます。
この300万円基準は、本格的なトレーダーにとって明確な指針となる「セーフハーバー(安全港)」ルールと見なせます。しかし、注意すべきは「収入の罠」です。たとえば、1回あたり4万円の取引を100回行った場合、収入金額は400万円となり300万円基準を超えます。しかし、もし利益率が低く、合計の利益がわずか数万円だったとしても、この基準に該当すれば事業所得としての複雑な会計処理が求められることになります。自身の取引スタイル(高頻度・低マージンか、低頻度・高マージンか)を考慮し、この基準の影響を理解することが重要です。
参考:暗号資産等に関する税務上の取扱いについて
過去の判例から見る、事業所得と判断されるポイント₿
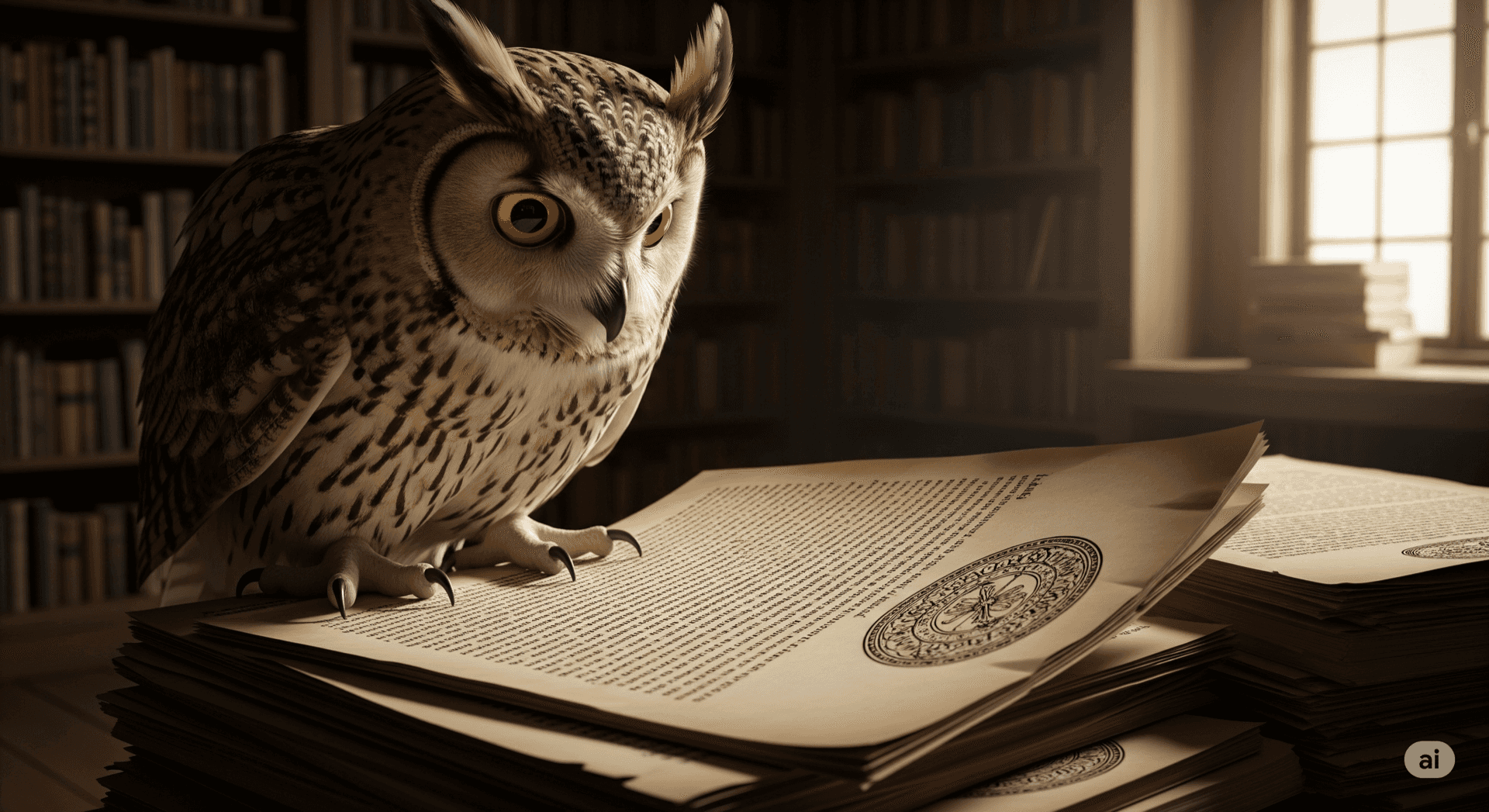
暗号資産取引に特化した最高裁判例はまだ多くありませんが、類似の金融商品であるFX(外国為替証拠金取引)に関する裁判例は、税務当局や裁判所が事業性をどのように判断するかの重要な手がかりとなります。
過去のFX取引に関する裁判例(例:東京高裁平成25年11月14日判決など)では、納税者が事業所得であると主張したものの、雑所得と判断されるケースが多く見られます。裁判所が重視したのは、以下のような客観的な事実です。
これらの判例からわかるのは、納税者自身が「事業だ」と認識しているだけでは不十分であり、その主張を裏付ける客観的で具体的な証拠(事業計画、資金管理、継続的な活動記録など)がなければ、裁判所や税務署を説得するのは難しいということです。
参考:東京高等 平成20年分所得税の更正請求控訴事件 平成25年11月14日
サラリーマン(給与所得者)でも事業所得として申告できる?₿

給与所得という安定した主たる収入源があるサラリーマンが、副業で行う暗号資産取引を事業所得として認めさせるのは、不可能ではありませんが、極めてハードルが高いと言えます。
税務署は、給与所得者が行う暗号資産取引を、基本的には資産運用や一時的な副収入(雑所得)と見なす傾向が強いです。この推定(正当と仮定すること)を覆すには、その取引が単なる趣味や資産運用の域をはるかに超え、独立した事業として成立していることを客観的な事実で証明する必要があります。たとえば、取引規模が極めて大きい、高度な専門知識やツールを駆使して継続的に多大な時間を費やしている、といった例外的な状況が求められます。
もし事業所得として申告を目指すのであれば、まず事業としての意思を明確にするために、税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を提出することが第一歩となります。
また、副業が会社に知られることを懸念する方も多いでしょう。確定申告の際、住民税の徴収方法で「自分で納付(普通徴収)」を選択すれば、副業分の住民税に関する通知が会社へ行くのを防ぐことができます。給与から天引きされる「特別徴収」を選ぶと、住民税額の変動から会社に副業の存在を推測される可能性があるため、この選択は重要です。
暗号資産を事業所得として確定申告する具体的な手続きと書き方₿
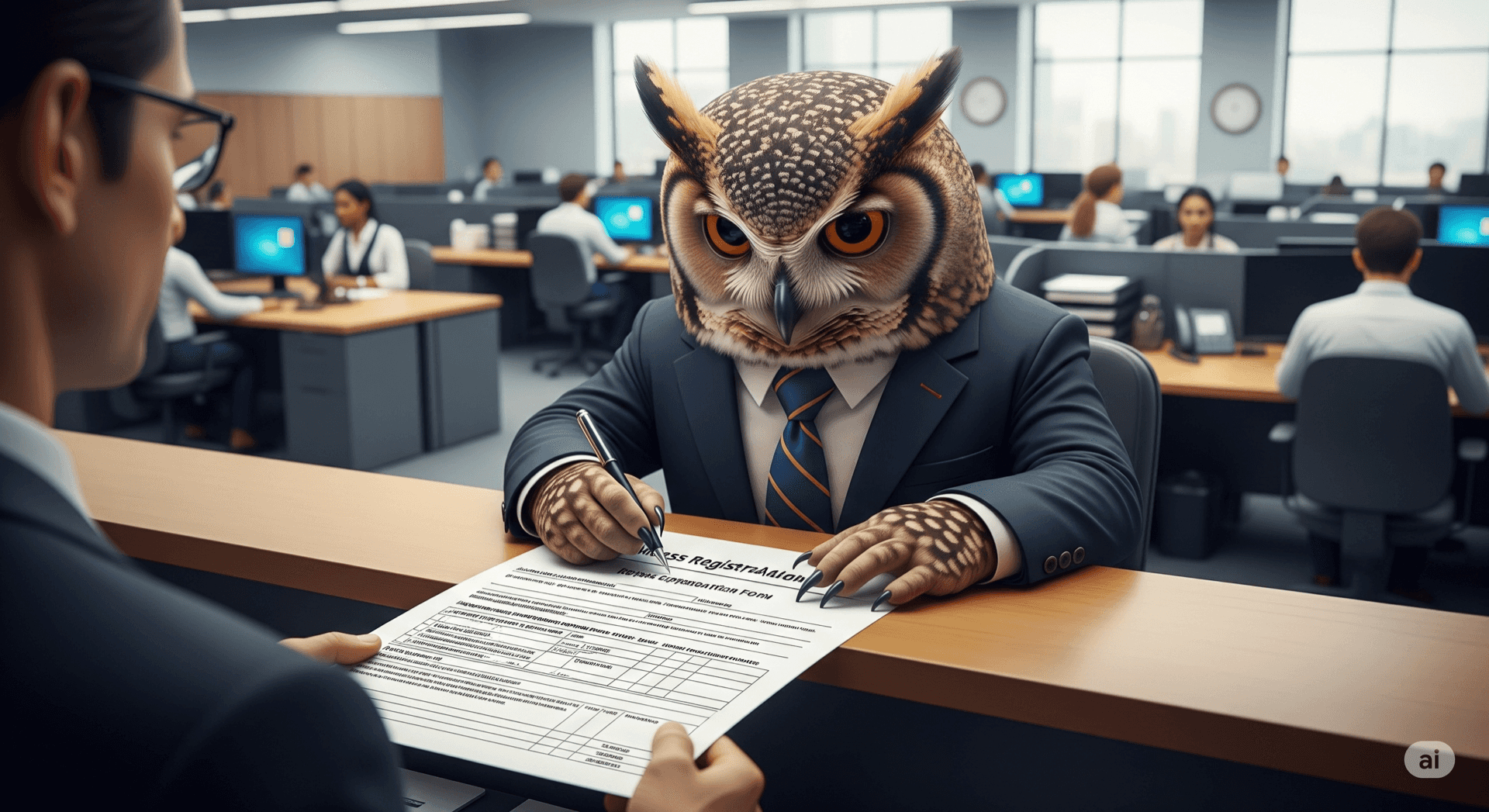
事業所得の条件を満たしていると判断した場合、次に必要となるのが具体的な申告手続きです。ここでは、開業届の提出から帳簿の作成、申告書の完成までの一連の流れを解説します。
- まずは「開業届」を税務署に提出する
- 事業所得申告に必須!帳簿の作成と保存方法
- 「年間取引報告書」から「収支内訳書」を作成する流れ
- 国税庁の「暗号資産の計算書」の活用方法
- 便利で簡単な「e-Tax」での確定申告のやり方
まずは「開業届」を税務署に提出する₿
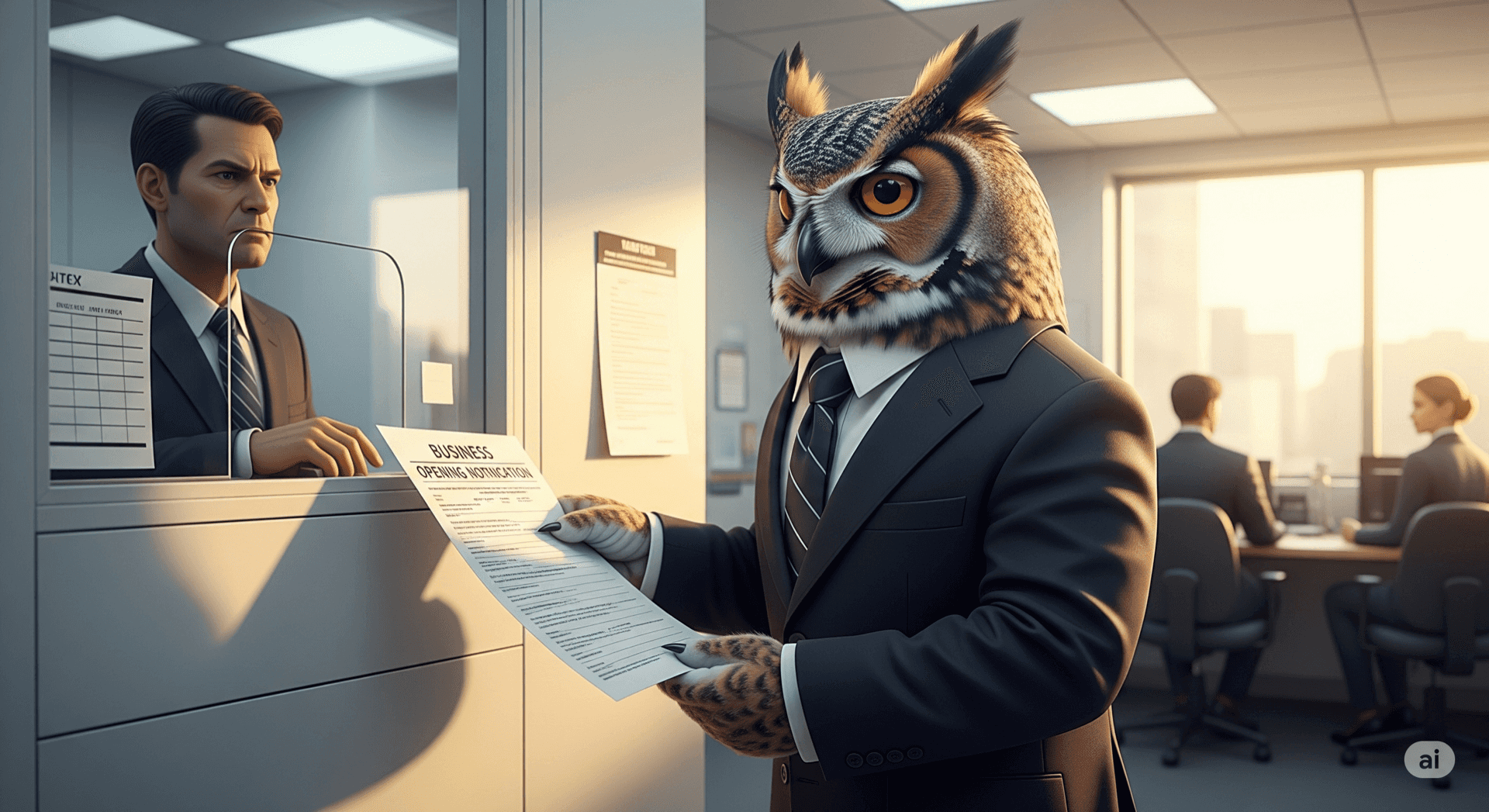
暗号資産取引を事業として正式に開始するための最初のステップは、「個人事業の開業・廃業等届出書」(通称:開業届)を納税地を管轄する税務署に提出することです。所得税法上、事業を開始した日から1か月以内の提出が定められています。
この開業届を提出する際に、青色申告のメリットを初年度から最大限に活用するため、「所得税の青色申告承認申請書」を同時に提出することを強く推奨します。青色申告承認申請書の提出期限は、事業開始日から2か月以内です(1月1日から15日までに開業した場合はその年の3月15日まで)。この期限を逃すと、その年は白色申告となり、青色申告の特典は翌年まで受けられなくなってしまうため、開業届とセットで手続きを済ませるのがもっとも効率的です。
事業所得申告に必須!帳簿の作成と保存方法₿
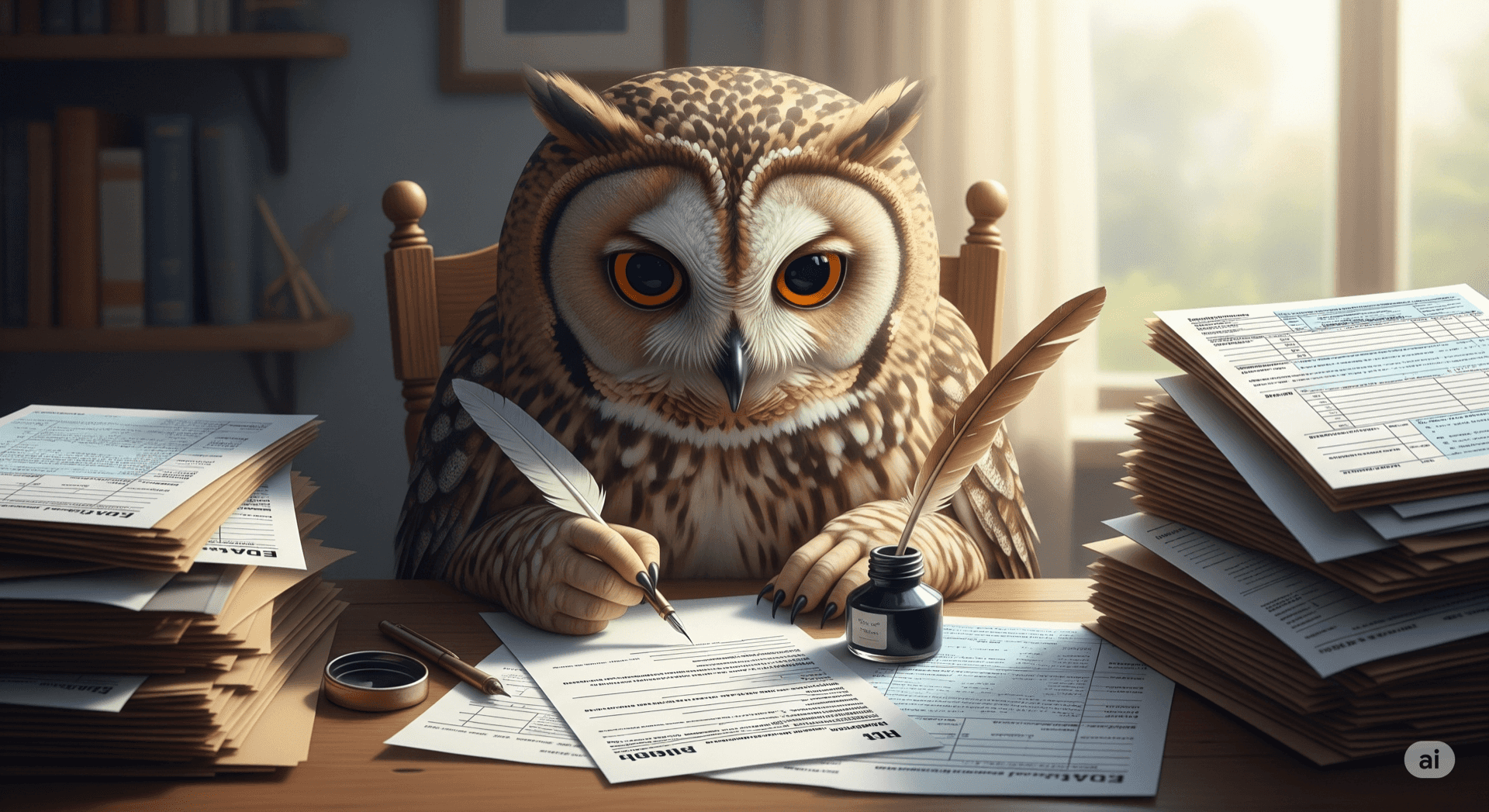
事業所得として申告する以上、日々の取引を記録した帳簿を作成し、一定期間保存することが法律で義務付けられています。申告方法によって求められる帳簿のレベルが異なります。
白色申告: 簡易な方法での記帳(簡易簿記)が認められています。収入と経費を日付順に記録する家計簿のような形式です。
青色申告(10万円控除): 白色申告と同様、簡易簿記での記帳が認められています。
青色申告(55万円/65万円控除): 正規の簿記の原則、すなわち「複式簿記」による記帳が必須です。すべての取引を借方と貸方に分けて記録し、期末には「貸借対照表(バランスシート)」と「損益計算書」を作成する必要があります。会計ソフトの利用が一般的です。なお、最高の65万円控除を受けるには、複式簿記に加えて、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。
表3: 申告種類別の帳簿要件とメリット
| 申告の種類 | 求められる帳簿 | 提出が必要な決算書類 | 主な税制上のメリット |
|---|
| 白色申告 | 簡易簿記 | 収支内訳書 | とくになし |
| 青色申告(10万円控除) | 簡易簿記 | 青色申告決算書 | 10万円の特別控除 |
| 青色申告(55万円控除) | 複式簿記 | 青色申告決算書(貸借対照表・損益計算書) | 55万円の特別控除、損失の繰越控除など |
| 青色申告(65万円控除) | 複式簿記+電子申告等 | 青色申告決算書(貸借対照表・損益計算書) | 65万円の特別控除、損失の繰越控除など |
「年間取引報告書」から「収支内訳書」を作成する流れ₿
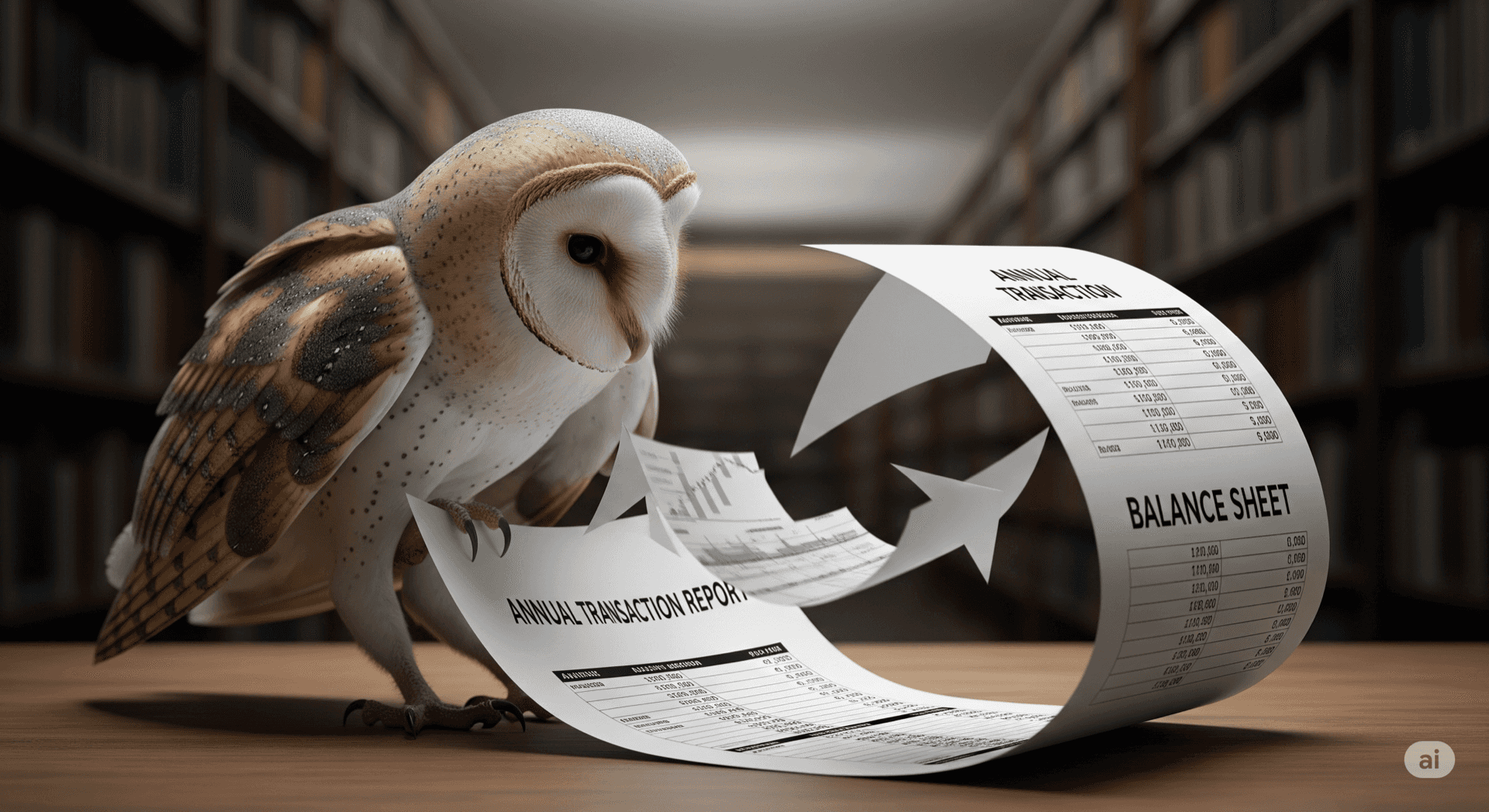
確定申告書類を作成する際の基礎資料となるのが、利用している暗号資産交換業者が発行する「年間取引報告書」です。この報告書には、年間の売買総額や手数料などがまとめられています。
資料の入手:
利用しているすべての交換業者から年間取引報告書をダウンロードします。
収入と経費の集計:
報告書を基に、年間の総収入金額(売上)と必要経費(取得価額、支払手数料など)を集計します。
収支内訳書への転記(白色申告の場合):
集計した金額を「収支内訳書」に転記します。暗号資産の売却による収入は「売上(収入)金額」の欄に、支払った手数料などは「経費」の該当項目(例:「支払手数料」や「雑費」)に記入します。
青色申告決算書への転記(青色申告の場合):
青色申告の場合は、より詳細な「青色申告決算書」を作成します。年間取引報告書のデータは、複式簿記で仕訳を行う際の元データとなり、最終的に損益計算書や貸借対照表に反映されます。
国税庁の「暗号資産の計算書」の活用方法₿
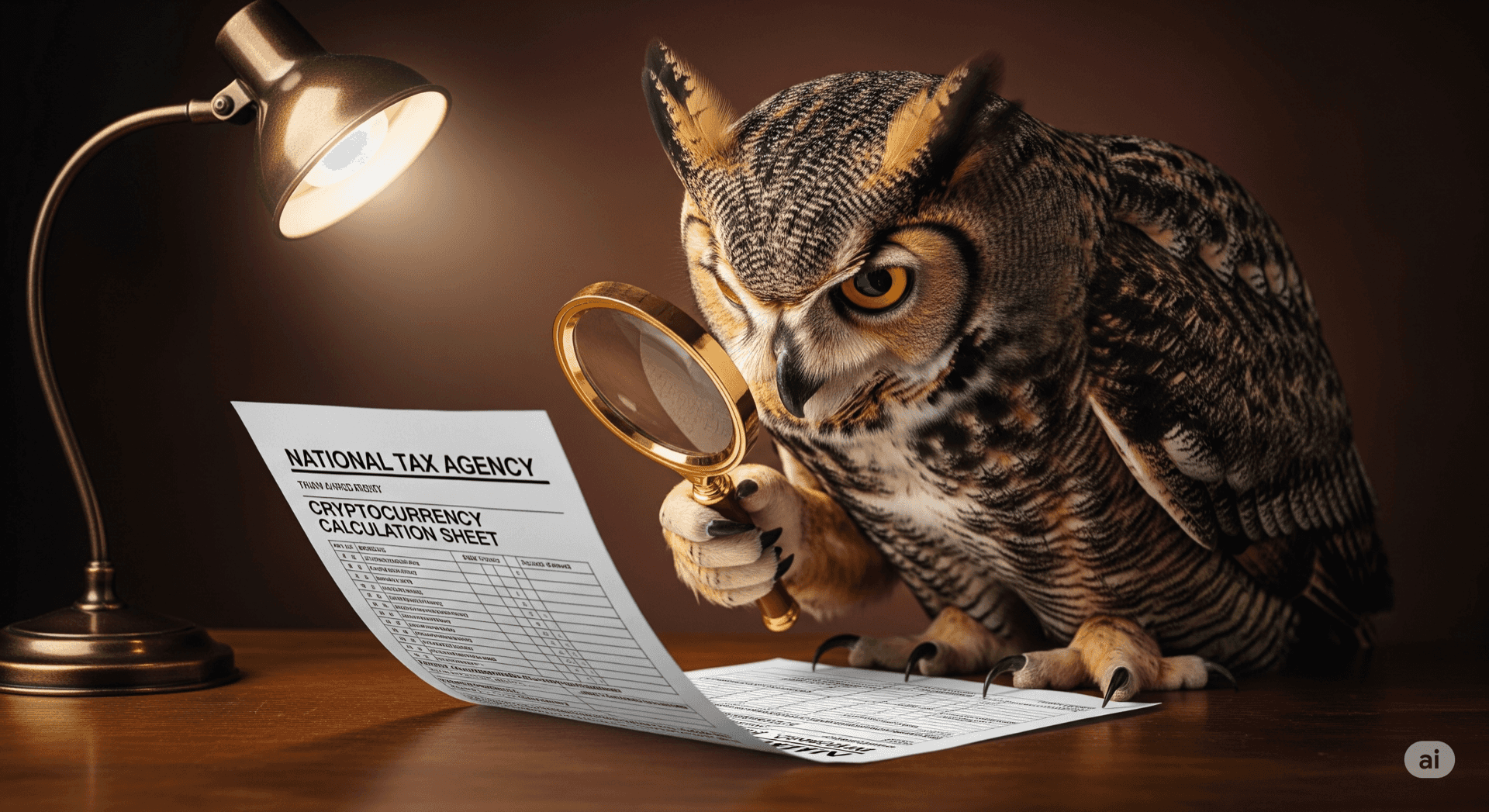
国税庁は、暗号資産の所得計算を支援するために、無料のExcel計算シート(「暗号資産の計算書」)を提供しています。とくに複数の暗号資産を取引している場合や、計算方法(総平均法・移動平均法)を正しく適用したい場合に非常に便利なツールです。
活用手順の概要:
ダウンロード:
国税庁のウェブサイトから、自身の採用する評価方法(総平均法または移動平均法)に合った計算書をダウンロードします。
シートの準備:
保有している暗号資産の銘柄ごとにシートを分け(取引所ごとではない点に注意)、シート名を銘柄名に変更します。
データ入力:
各銘柄のシートに、年間取引報告書の内容(年間購入数量・金額、年間売却数量・金額、支払手数料など)を転記します。
その他の取引の入力:
年間取引報告書に記載されない取引(暗号資産同士の交換、商品購入時の決済利用、ステーキングやDeFiで得た報酬など)も手動で入力します。
所得金額の確認:
すべての取引を入力すると、シートが自動的に所得金額を計算してくれます。この最終的な金額を、確定申告書の該当欄に転記します。
参考:暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和6年12月)|国税庁
広告
便利で簡単な「e-Tax」での確定申告のやり方₿
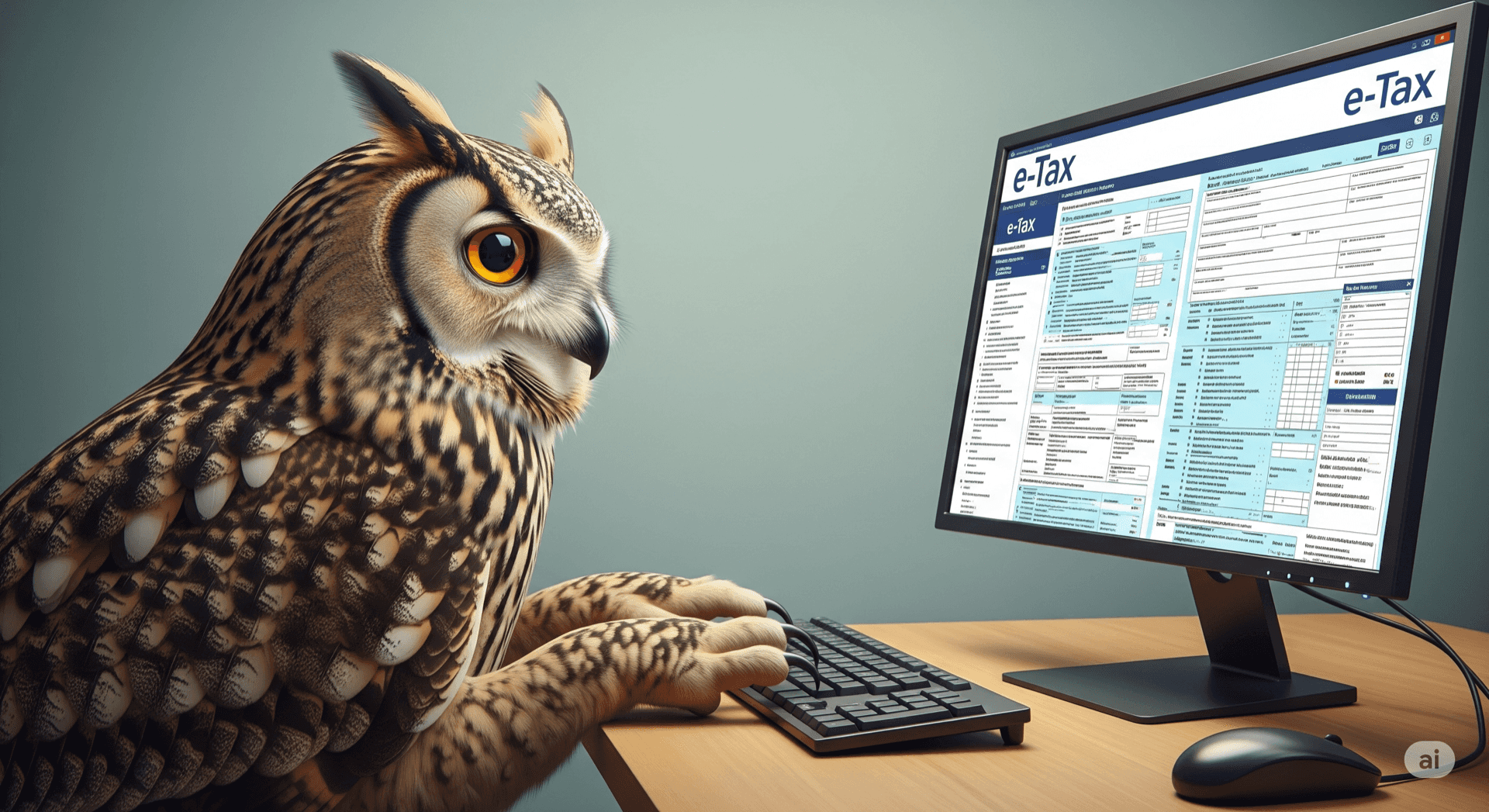
作成した確定申告書類は、国税電子申告・納税システム「e-Tax」を利用してオンラインで提出するのがもっとも効率的です。とくに、青色申告で65万円の特別控除を受けるためにはe-Taxでの申告が必須条件となります。
e-Tax申告(マイナンバーカード方式)の概要:
準備:
マイナンバーカードと、それを読み取るためのICカードリーダライター、またはマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンを用意します。
ログイン:
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、「マイナンバーカード方式」を選択してログインします。スマートフォンの「マイナポータルアプリ」を使ってQRコードを読み取ることで、簡単に認証できます。
申告書作成:
画面の案内にしたがって、住所・氏名などの基本情報、給与所得や事業所得の金額(「暗号資産の計算書」で算出した所得額など)を入力します。マイナポータルと連携すれば、控除証明書などのデータを自動で取り込み、入力の手間を省くことも可能です。
送信:
すべての入力が終わると、システムが自動で申告書を作成します。内容を確認後、マイナンバーカードを使って電子署名を行い、データを送信すれば申告手続きは完了です。
参考:スマホとマイナンバーカードでe-Tax!|令和6年分 確定申告特集
広告
暗号資産の事業所得を総括₿
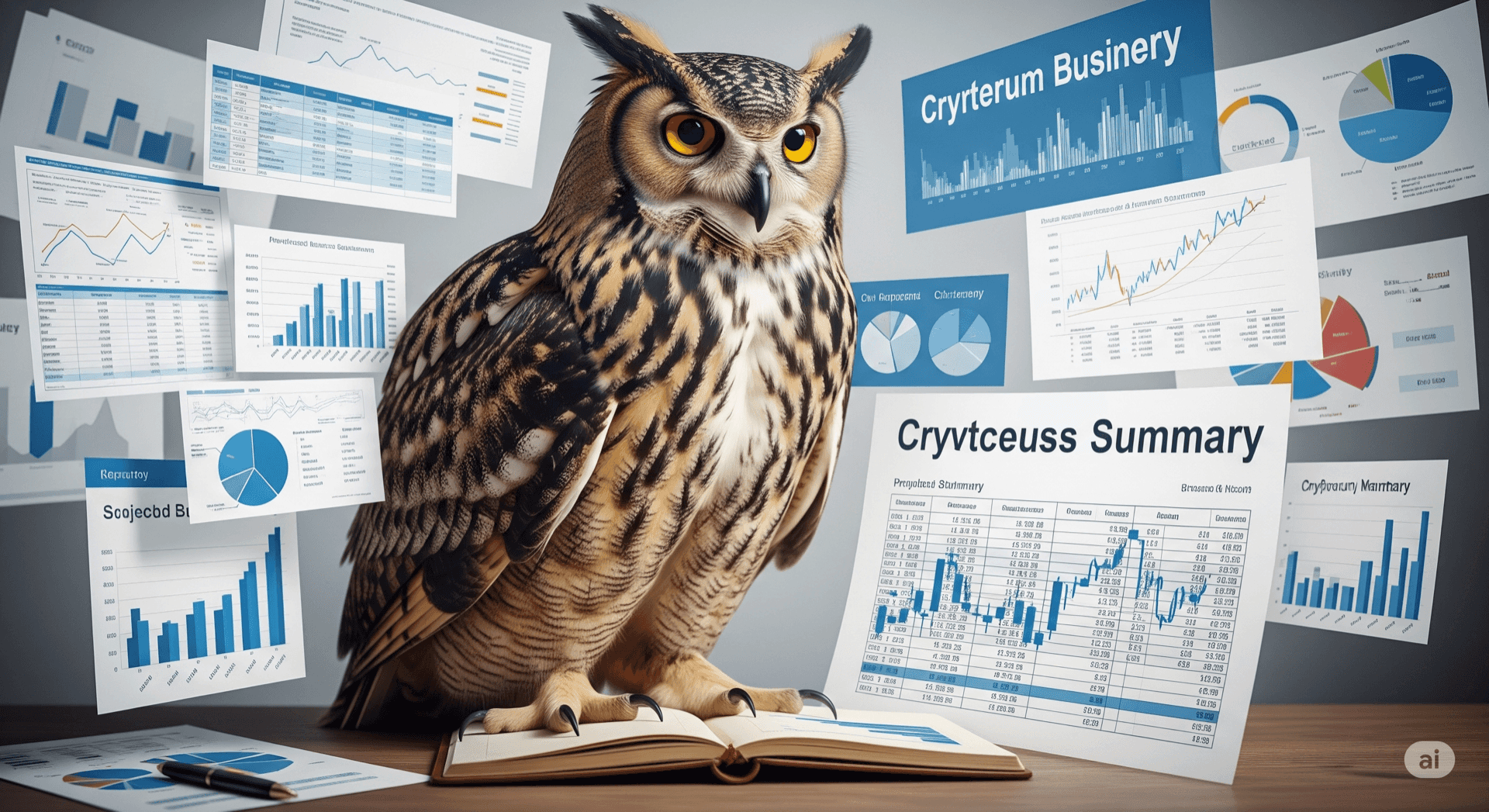
まとめ:事業所得のメリットは大きいが、条件を満たしているか慎重な判断を₿
暗号資産取引で得た利益を「事業所得」として申告することは、損益通算や青色申告特別控除、損失の繰越控除といった、税制上の大きなメリットを享受できる可能性があります。とくに価格変動の激しい市場で活動するアクティブなトレーダーにとって、これらの制度は税負担を平準化し、安定した取引を続ける上で強力な武器となり得ます。
しかし、そのメリットを享受するためには、相応の対価が求められます。開業届の提出に始まり、複式簿記による厳格な帳簿作成と保存の義務、そして何よりも「事業」と客観的に認められるだけの活動実態が不可欠です。国税庁が示した「300万円基準」は1つの目安にはなりますが、それを満たしていても事業性が伴わなければ否認されるリスクは残ります。
安易に節税メリットだけをみて事業所得として申告するのではなく、ご自身の取引の規模、頻度、費やしている時間や労力などを国税庁の基準や過去の判例に照らし合わせ、その実態が社会通念上「事業」と呼べるものか、慎重に自己評価することが極めて重要です。
もしご自身の状況が事業所得に該当するかどうか判断に迷う場合や、取引が複雑で大規模な場合には、安易な自己判断は避け、暗号資産の税務に精通した税理士などの専門家に相談することを強く推奨します。適切な申告こそが、将来の予期せぬ追徴課税やペナルティを回避し、安心して資産形成を続けるための最善策です。
参考:確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
広告
更新