暗号資産の総平均法とは?確定申告のための所得計算方法を徹底解説
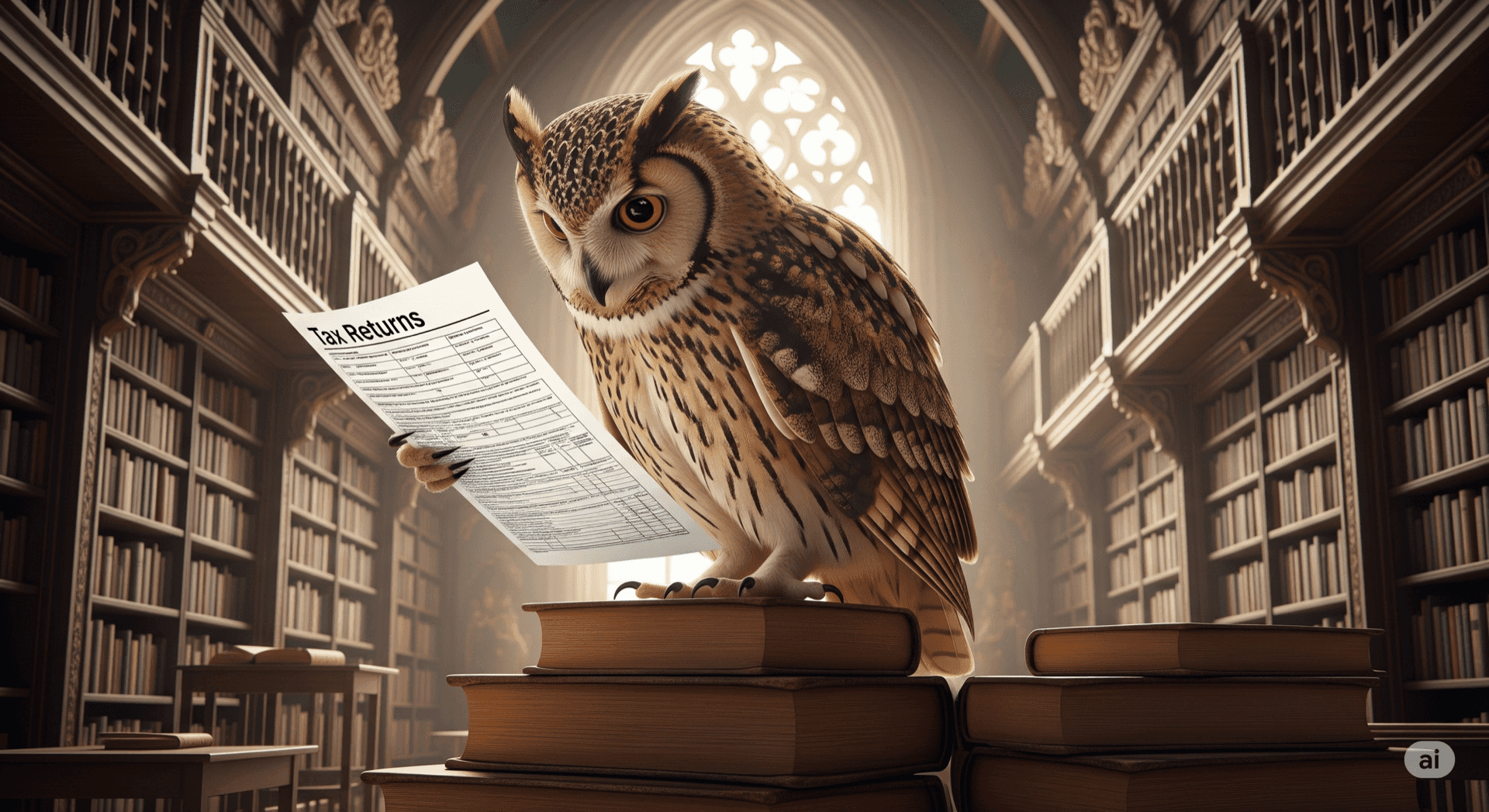
暗号資産(仮想通貨)の取引によって利益が生じた場合、その所得を正確に計算し、確定申告を行うことは納税者の義務です。所得計算にはいくつかの方法が存在しますが、この記事では、個人投資家にとってもっとも基本的かつ重要な計算方法である「総平均法」に焦点を当てます。
総平均法の基本的な仕組みから、具体的な計算手順、年をまたいで資産を保有する場合の取り扱い、そしてもう1つの主要な計算方法である「移動平均法」との詳細な比較まで、専門的な観点から徹底的に解説します。さらに、国税庁が提供する計算ツールの活用法、評価方法の届出の要否といった実務的な論点、そして複雑化する取引に対応するための市販ツールについても分析します。これにより、納税者が自身の取引スタイルに最適な方法を理解し、確実な確定申告を遂行するための包括的な知識を提供します。
目次を表示
暗号資産の総平均法とは₿
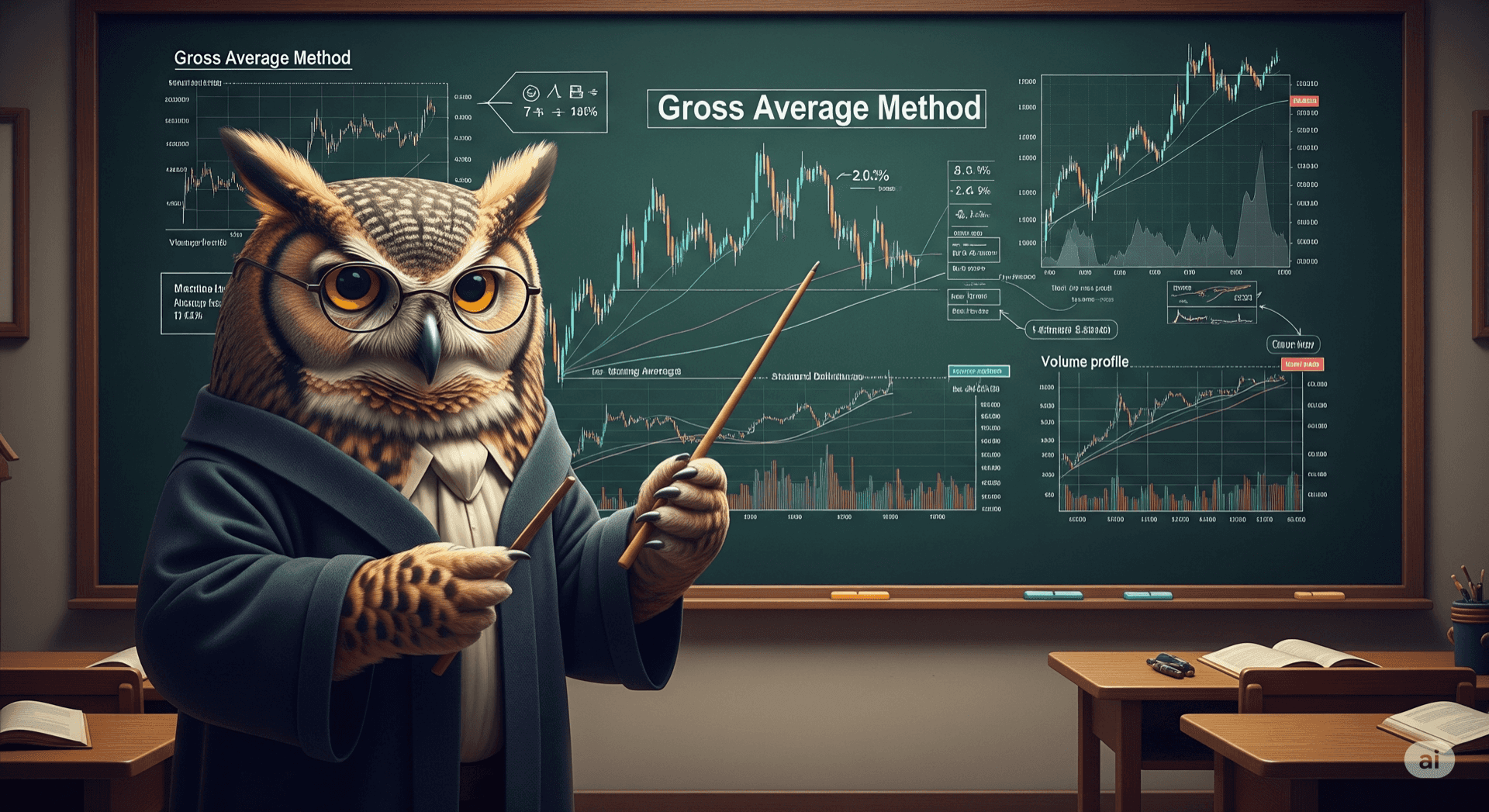
暗号資産の所得計算における総平均法は、その計算の簡便さから多くの個人投資家にとって基本となる評価方法です。ここでは、その概念的な枠組みから法的な位置づけ、具体的な計算プロセス、そしてその利点と欠点について多角的に掘り下げていきます。
- 総平均法の基本的な考え方
- 法定評価方法としての総平均法 - 届出は必要か?
- 【具体例】総平均法の計算ステップ
- 年をまたぐ場合の計算方法(年またぎ)
- メリット:計算がシンプルで分かりやすい
- デメリット:期中の損益が把握しにくい
総平均法の基本的な考え方₿

総平均法とは、特定の暗号資産について、1年間(1月1日〜12月31日)に購入したすべての資産の取得価額の合計額を、同期間に購入した総数量で割り、その年の平均取得単価を算出する方法です。この計算は、年間の取引がすべて完了した後に一度だけ行われます。
算出された平均取得単価は、その年に売却したすべての暗号資産の原価(売却原価)を計算するために用いられます。具体的には、「売却価格」から「平均取得単価 × 売却数量」で計算される「売却原価」を差し引くことで、その年の課税対象となる所得金額が確定します。この方法の最大の特徴は、取引の回数やタイミングにかかわらず、年間の平均コストを一度だけ算出すればよいため、計算プロセスが非常にシンプルになる点です。
法定評価方法としての総平均法 - 届出は必要か?₿
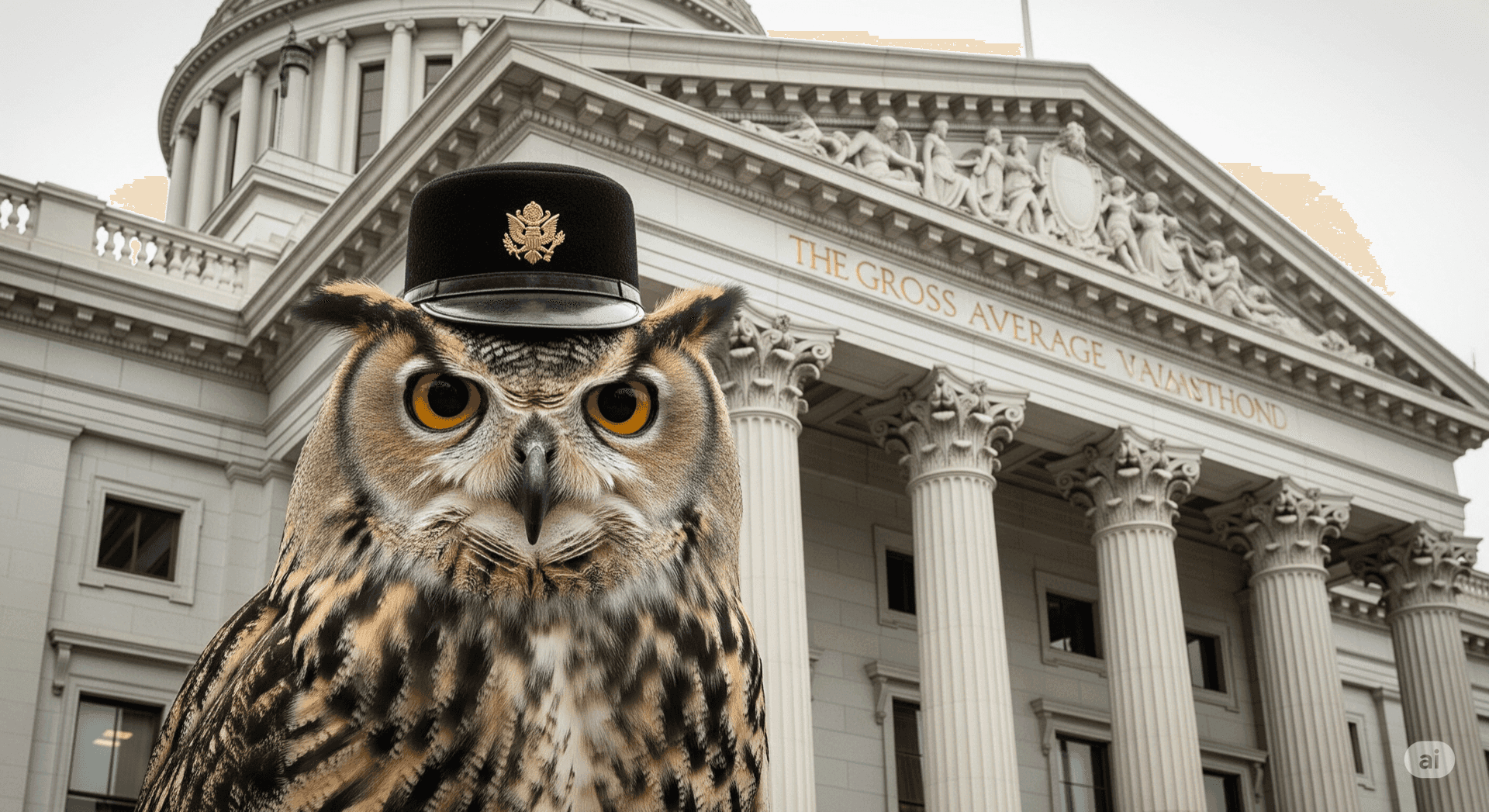
個人投資家にとって極めて重要な点として、暗号資産の評価方法は、税務署へ事前の届出を行わない限り、自動的に「総平均法」が適用されると法律で定められています。これを「法定評価方法」と呼びます。
この規定の法的根拠は、所得税法施行令第119条の3にあります。したがって、総平均法を用いて確定申告を行う個人投資家は、原則として「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を税務署に提出する必要はありません。
一方で、後述する「移動平均法」を選択したい場合には、この届出書の提出が必須となります。届出は、その暗号資産をはじめて取得した年分の確定申告期限までに行う必要があります。この手続きを怠ると、意図せず総平均法で計算せざるを得なくなるため、注意が必要です。つまり、総平均法は「何もしない場合のデフォルト設定」であり、移動平均法は「能動的に選択する必要があるオプション」と理解することが重要です。
参考:所得税法施行令(暗号資産の評価の方法の選定)第百十九条の三
【具体例】総平均法の計算ステップ₿
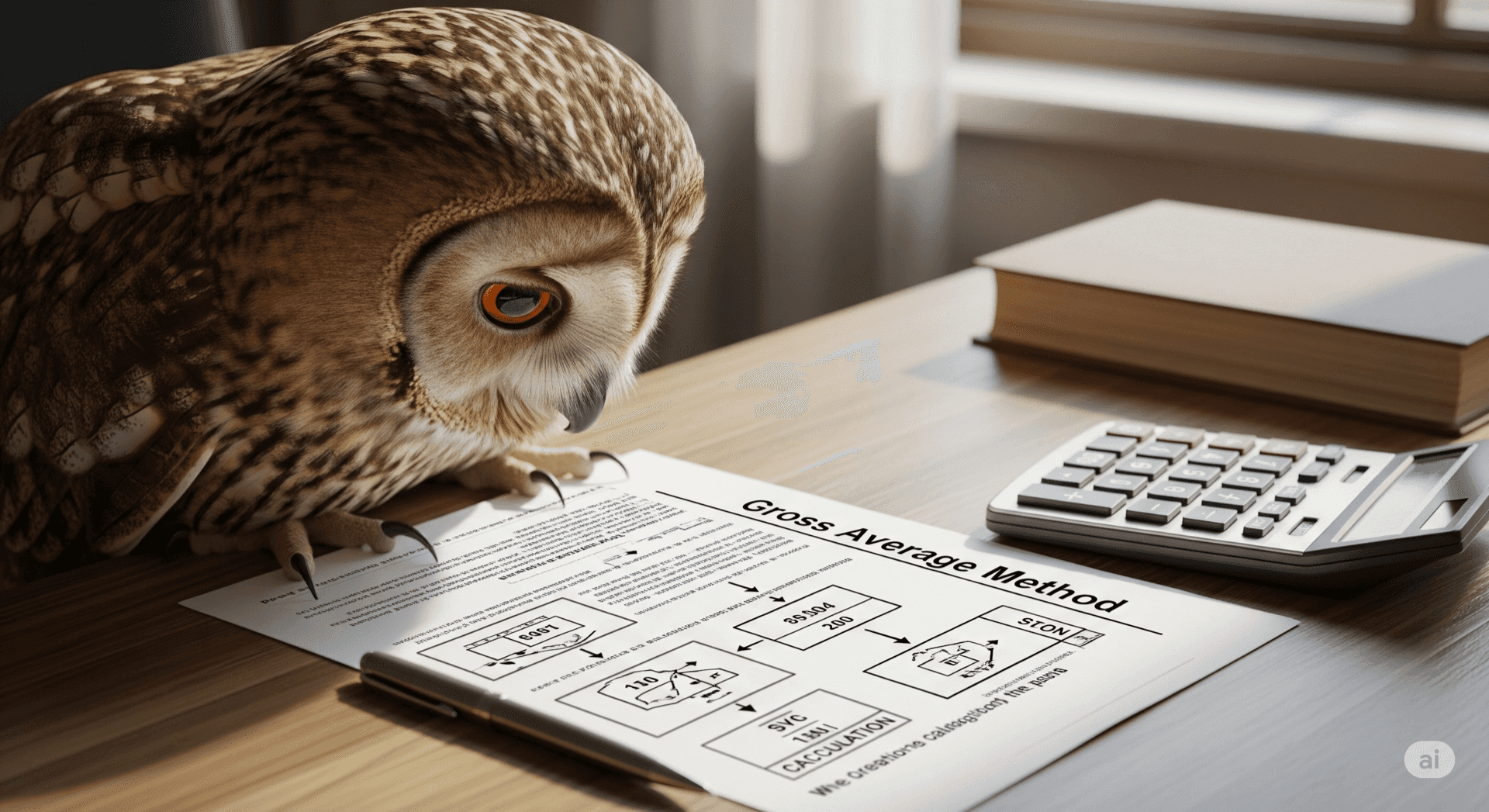
総平均法による所得計算の具体的な流れを、以下の例に沿って解説します。
前提条件:
1年間にビットコイン(BTC)を3回購入
1回目: 1 BTC を 300万円で購入
2回目: 0.5 BTC を 200万円で購入
3回目: 0.5 BTC を 250万円で購入
同一年内に、1.5 BTC を 750万円で売却
ステップ1:年間の総購入金額と総購入数量の集計
まず、1年間の購入取引をすべて集計します。
ステップ2:平均単価(取得価額)の算出
次に、ステップ1で集計した数値を基に、1 BTCあたりの平均単価を計算します。
平均単価 = 総購入金額 ÷ 総購入数量
7,500,000円÷2BTC=3,750,000円/BTC
この375万円が、この年のBTCの取得価額となります。
ステップ3:売却による所得の計算
最後に、算出した平均単価を用いて売却による所得を計算します。
売却価格 = 750万円
売却原価 = 平均単価 × 売却数量 = 3,750,000円/BTC × 1.5 BTC = 5,625,000円
所得金額 = 売却価格 - 売却原価 = 7,500,000円 - 5,625,000円 = 1,875,000円
この1,875,000円が、この年のBTC取引に関する雑所得として申告すべき金額となります。なお、取引手数料を日本円で支払った場合は、別途「必要経費」として所得金額から差し引くことができます。手数料を暗号資産で支払った場合は、その手数料分の暗号資産を売却したとみなして損益を計算する必要があり、より複雑な処理が求められます。
年をまたぐ場合の計算方法(年またぎ)₿

前年から暗号資産を保有している場合、その資産の評価額と数量を当年の計算に含める必要があります。これは、総平均法がその年に売却した資産の原価を、過去に取得したものも含めたすべての保有資産の平均コストで計算するためです。
国税庁が示す正式な計算式は以下の通りです。
平均単価=(前年末の残高の評価額+当該年中の取得価額の合計額)÷(前年末の残高の数量+当該年中の取得数量の合計)
具体例:
前年末に、平均単価300万円で1 BTCを保有していたとします。これを上記の例に加えると、計算は以下のようになります。
総購入金額(分子)= (前年末の評価額: 300万円 × 1 BTC) + (当年の総購入金額: 750万円) = 1,050万円
総購入数量(分母)= (前年末の数量: 1 BTC) + (当年の総購入数量: 2 BTC) = 3 BTC
新・平均単価= 1,050万円 ÷ 3 BTC = 350万円/BTC
この新しい平均単価350万円を用いて、当年の売却益を再計算します。
このように、前年からの繰越資産がある場合、その年の平均単価と所得金額が変動します。毎年、前年末の残高を正確に引き継いで計算を更新していくことが不可欠です。
メリット:計算がシンプルで分かりやすい₿
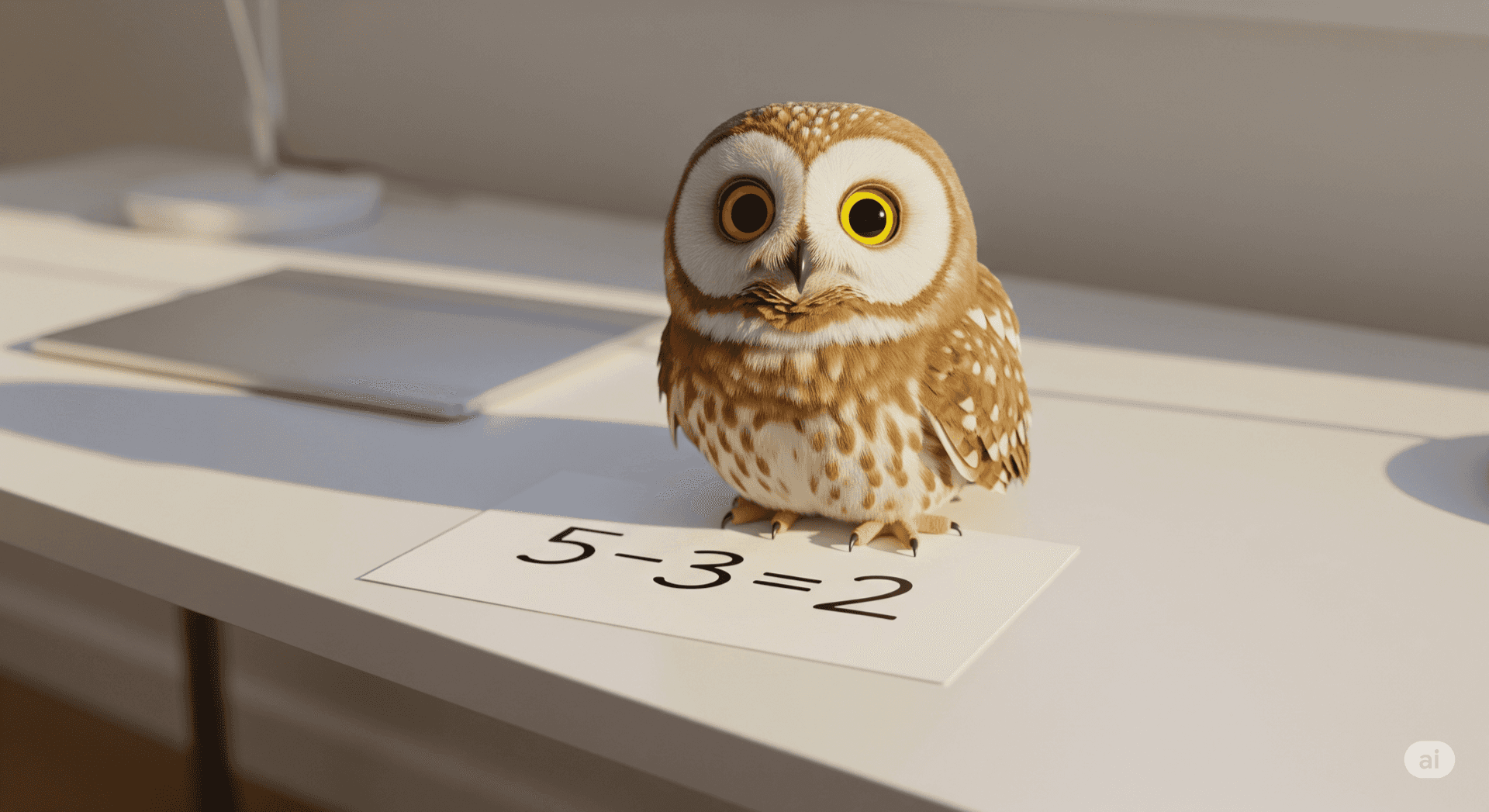
総平均法の最大のメリットは、その計算方法の単純明快さにあります。年間の購入取引データをすべて集計し、平均単価を一度だけ算出すれば、その年のすべての売却取引の原価計算が完了します。取引回数が数百、数千回に及ぶトレーダーであっても、計算の負担は比較的小さく、間違いも起こりにくいです。
とくに、多くの暗号資産交換業者が提供する「年間取引報告書」と、国税庁がウェブサイトで公開している「暗号資産の計算書(総平均法用)」を組み合わせることで、報告書の数値を計算書に転記するだけで所得金額が自動的に算出されるため、確定申告の準備を非常に効率的に進めることができます。
デメリット:期中の損益が把握しにくい₿
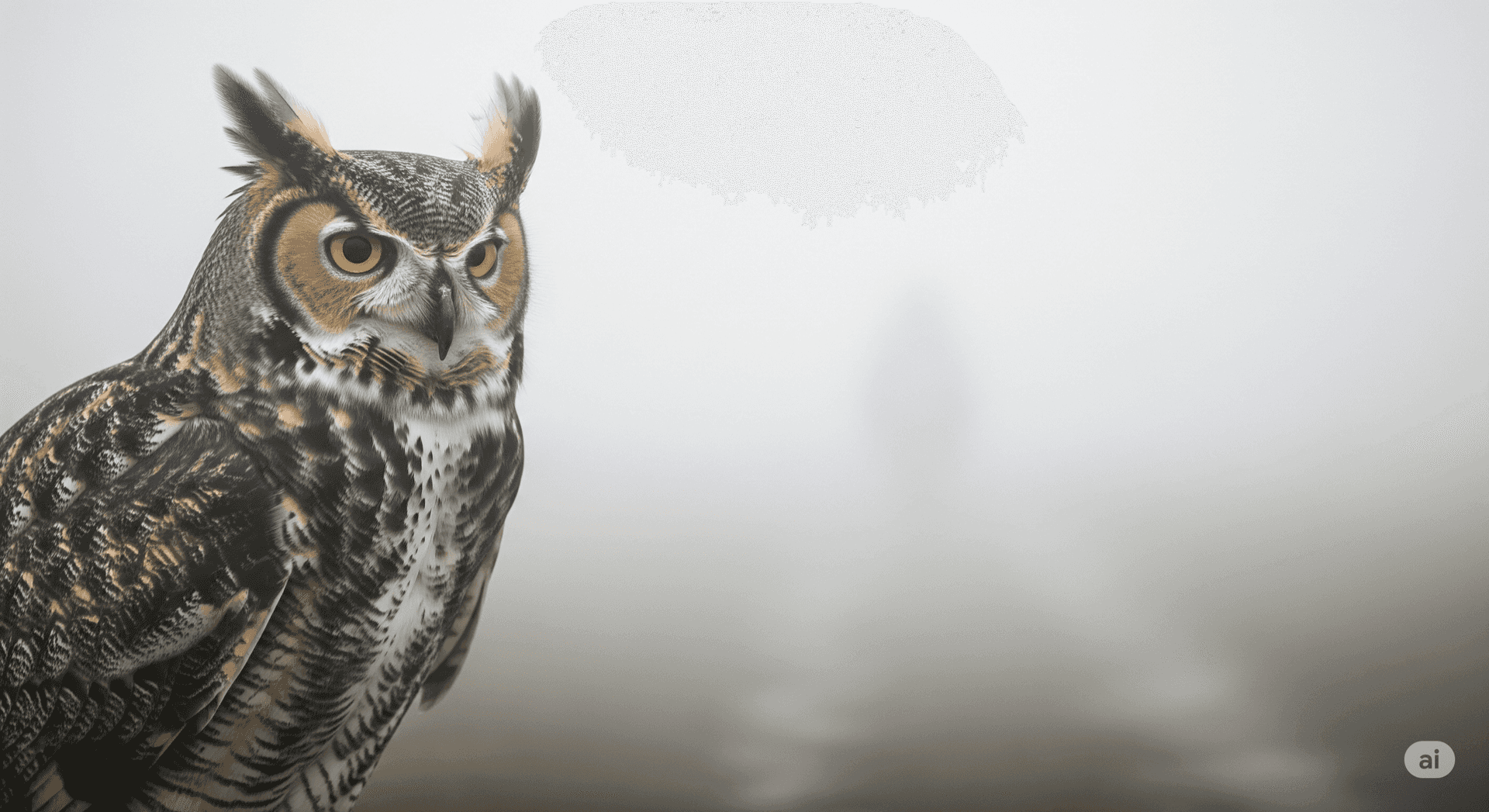
一方で、総平均法の最大のデメリットは、年間の取引がすべて完了するまで正確な平均単価が確定しない点です。たとえば、年の前半に利益が出ていると思って暗号資産を売却しても、年末にかけて価格が下落したタイミングで買い増しを行うと、年間の平均単価が上昇し、結果的に当初見込んでいた利益が減少、あるいは損失に転じる可能性すらあります。
この特性により、年間の途中で「現時点でどれくらいの利益または損失が出ているのか」を正確に把握することが極めて困難になります。その結果、計画的な利益確定(利確)や損失確定(損切り)、あるいは納税資金を計画的に準備するといったタックスプランニングが非常に立てづらくなるという、戦略上の大きな欠点を抱えています。
この「法定評価方法」であることの裏には、納税者の利便性を優先する国税庁の方針が見えますが、それは同時に、個々の投資家が自身の納税額を最適化する機会を逸するリスクもはらんでいます。日本の所得税は所得額に応じて税率が上がる累進課税制度を採用しているため、どの年にどれだけの利益を計上するかは、複数年にわたる総納税額に直接影響します。総平均法と移動平均法では、生涯にわたる総利益額は同じでも、利益が計上される年がずれることで、適用される税率が変わり、最終的な手取り額に差が生じる可能性があるのです。したがって、単に「簡単だから」という理由で総平均法を選択することは、必ずしも賢明な判断とは言えない場合があります。
暗号資産の総平均法の解説₿
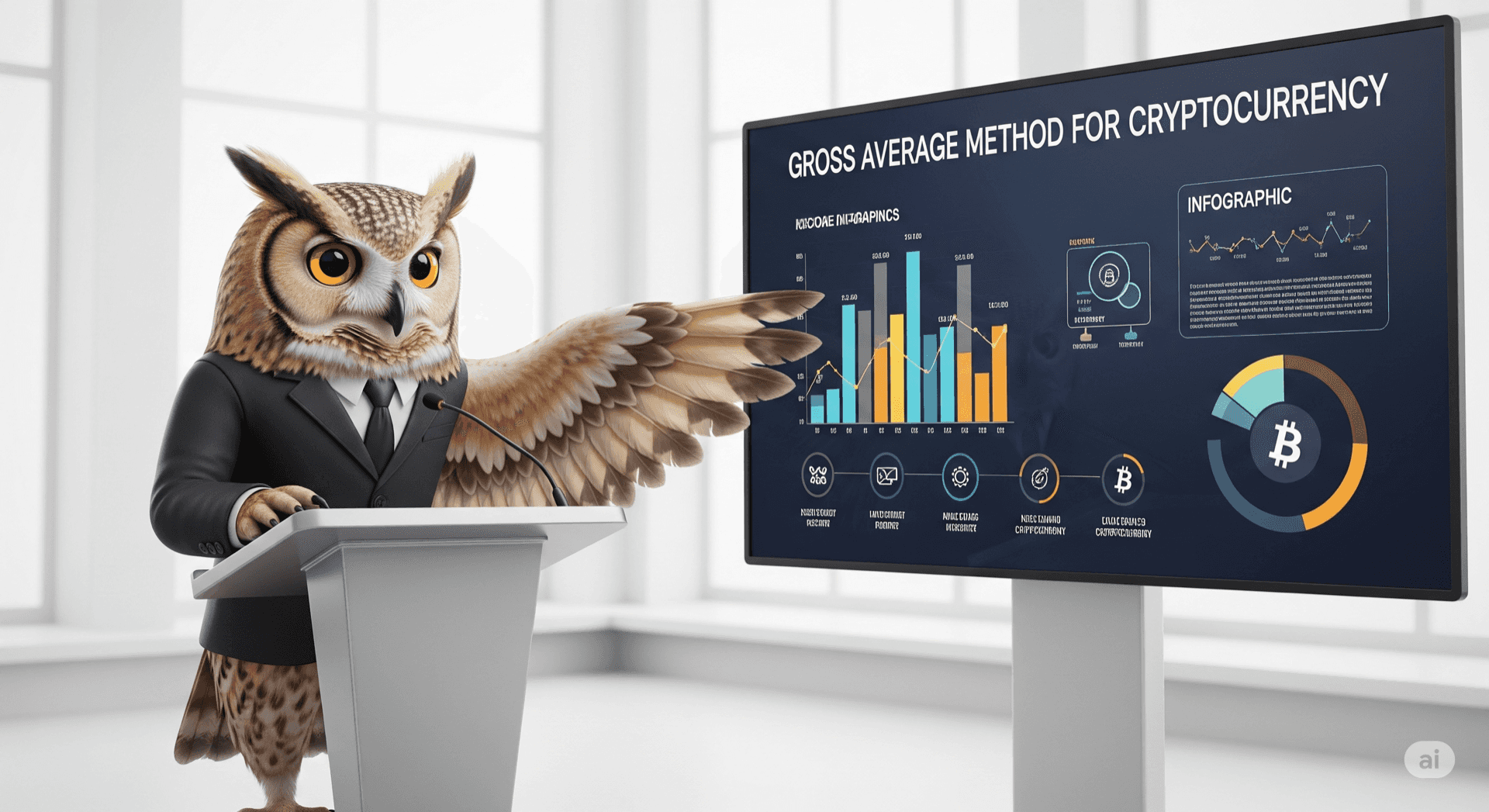
総平均法を実際に用いて確定申告を行うための具体的な手法や、より深い分析、そして関連する重要なルールについて解説します。国税庁のツール活用から、もう1つの計算方法である移動平均法との戦略的な比較まで、実践的な知識を網羅します。
- 国税庁提供「暗号資産の計算書(総平均法用)」の活用
- エクセル(Excel)を使った手動計算の方法
- 総平均法と移動平均法、どちらを選ぶべき?
- 「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を提出していない場合
- ビットコイン(BTC)など主要通貨の計算例
- 便利な暗号資産の税金計算ツール
- 暗号資産の総平均法を総括
国税庁提供「暗号資産の計算書(総平均法用)」の活用₿

確定申告の負担を軽減するため、国税庁は公式ウェブサイトで「暗号資産の計算書(総平均法用)」というExcel形式の計算ツールを無料で提供しています。このツールは、総平均法による所得計算を自動化するために設計されており、多くの個人投資家にとって非常に有用です。
活用手順の概要:
ツールの入手:国税庁のウェブサイトから最新版のExcelファイルをダウンロードします。
年間取引報告書の準備:利用しているすべての暗号資産交換業者から「年間取引報告書」を取得します。
データ転記:報告書に記載されている通貨ごとの「年間の購入数量・金額」および「年間の売却数量・金額」を、計算書の「2 年間取引報告書に関する事項」の欄に転記します。
その他の取引の入力:個人間取引やマイニング、ステーキング報酬など、年間取引報告書に含まれない取引は、「3 上記2以外の取引に関する事項」に手動で入力します。
年始残高の入力:前年から資産を保有している場合は、前年の計算書から年末残高の数量と金額を「4 暗号資産の売却原価の計算」の年始残高欄に入力します。
所得金額の自動計算:上記の入力が完了すると、Excelシートが自動的に総平均単価、売却原価、そして最終的な所得金額を「5 暗号資産の所得金額の計算」の欄で算出してくれます。
この計算書は、確定申告書を作成する際の基礎資料となり、申告書に添付して提出します。ただし、計算は暗号資産の種類ごとに行う必要があるため、たとえばビットコインとイーサリアムの両方を取引している場合は、それぞれ別のシート(または別のファイル)で計算する必要がある点に注意が必要です。
参考:暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和6年12月)|国税庁
エクセル(Excel)を使った手動計算の方法₿
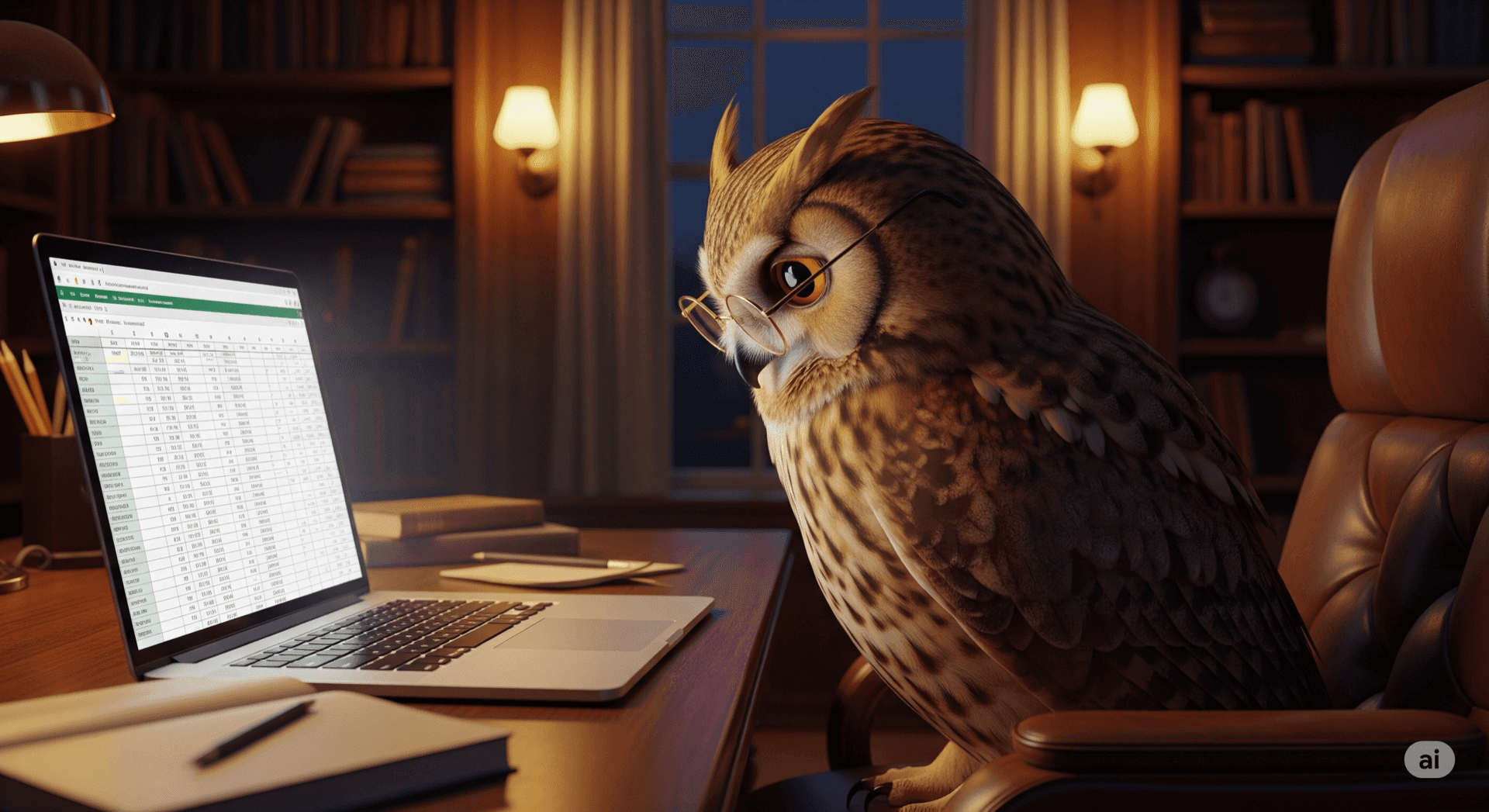
国税庁の計算書は便利ですが、DeFi(分散型金融)やNFT取引など、そのフォーマットに収まらない複雑な取引を行っている場合は、自身でExcelなどを用いて手動で計算・管理する必要があります。その際に不可欠となるのが、すべての取引に関する詳細な記録です。
最低限、以下の項目を取引ごとに記録しておく必要があります。
これらのデータを基に、通貨ごとに年間の総購入金額と総購入数量をSUMIF関数などで集計し、総平均法の計算式に当てはめて平均単価を算出します。この地道な記録管理が、正確な申告の礎となります。
総平均法と移動平均法、どちらを選ぶべき?₿

暗号資産の所得計算には、総平均法と並んで「移動平均法」というもう1つの主要な方法があります。移動平均法は、暗号資産を取得するたびに、その時点での保有資産全体の平均単価を計算し直す方法です。
どちらの計算方法を選択すべきか、その判断材料として両者の特徴を比較します。
表1:総平均法と移動平均法の特長比較
| 項目 | 総平均法 | 移動平均法 |
|---|
| 計算タイミング | 年に1回、期末にまとめて計算 | 暗号資産を購入する都度、計算 |
| 計算の煩雑さ | 簡単で、取引回数が多くても対応しやすい | 非常に煩雑で、取引回数が多いと手計算は困難 |
| 期中の損益把握 | 年末まで正確な損益は不明確 | 売却の都度、その時点での損益を正確に把握可能 |
| タックスプランニング | 計画的な節税対策が困難 | 損益を把握しやすいため、計画的な利確や損切りが可能 |
| 届出の要否(個人) | 原則不要(法定評価方法) | 必須(確定申告期限までに届出が必要) |
シナリオ分析:どちらが有利か?
どちらの方法が税務上有利になるかは、その年の相場状況や個人の取引パターン、そして所得状況によって異なります。単純な比較だけでは見えない、その本質的な違いをシミュレーションで明らかにします。
シナリオ:価格が上昇トレンドにある年
| 計算方法 | 計算過程 | 算出される所得 |
|---|
| 総平均法 | 年間平均単価 = (300万円 + 700万円) ÷ (1 BTC + 1 BTC) = 500万円/BTC
売却原価 = 500万円/BTC × 0.5 BTC = 250万円
所得 = 500万円 - 250万円 | 250万円 |
| 移動平均法 | 6月1日の売却時点での平均単価 = 300万円/BTC
売却原価 = 300万円/BTC × 0.5 BTC = 150万円
所得 = 500万円 - 150万円 | 350万円 |
このシミュレーションからわかるように、同じ取引でも計算方法によってその年に認識される所得額が大きく異なります。このケースでは、総平均法の方が所得が低く計算され、その年の納税額は少なくなります。しかし、これは利益が消えたわけではなく、年末に残った資産の簿価が移動平均法の場合よりも低くなるため、翌年以降に売却した際の利益がその分大きくなる形で、利益認識が将来に繰り延べられているに過ぎません。
したがって、「どちらが有利か」という問いへの答えは、「どの年に利益を計上したいか」によります。他の所得が多く、高い税率が適用される年に利益を圧縮したい場合は総平均法が有利に働く可能性があります。逆に、他の所得が少ない年に利益を確定させたい場合は、移動平均法が適しているかもしれません。
「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を提出していない場合₿
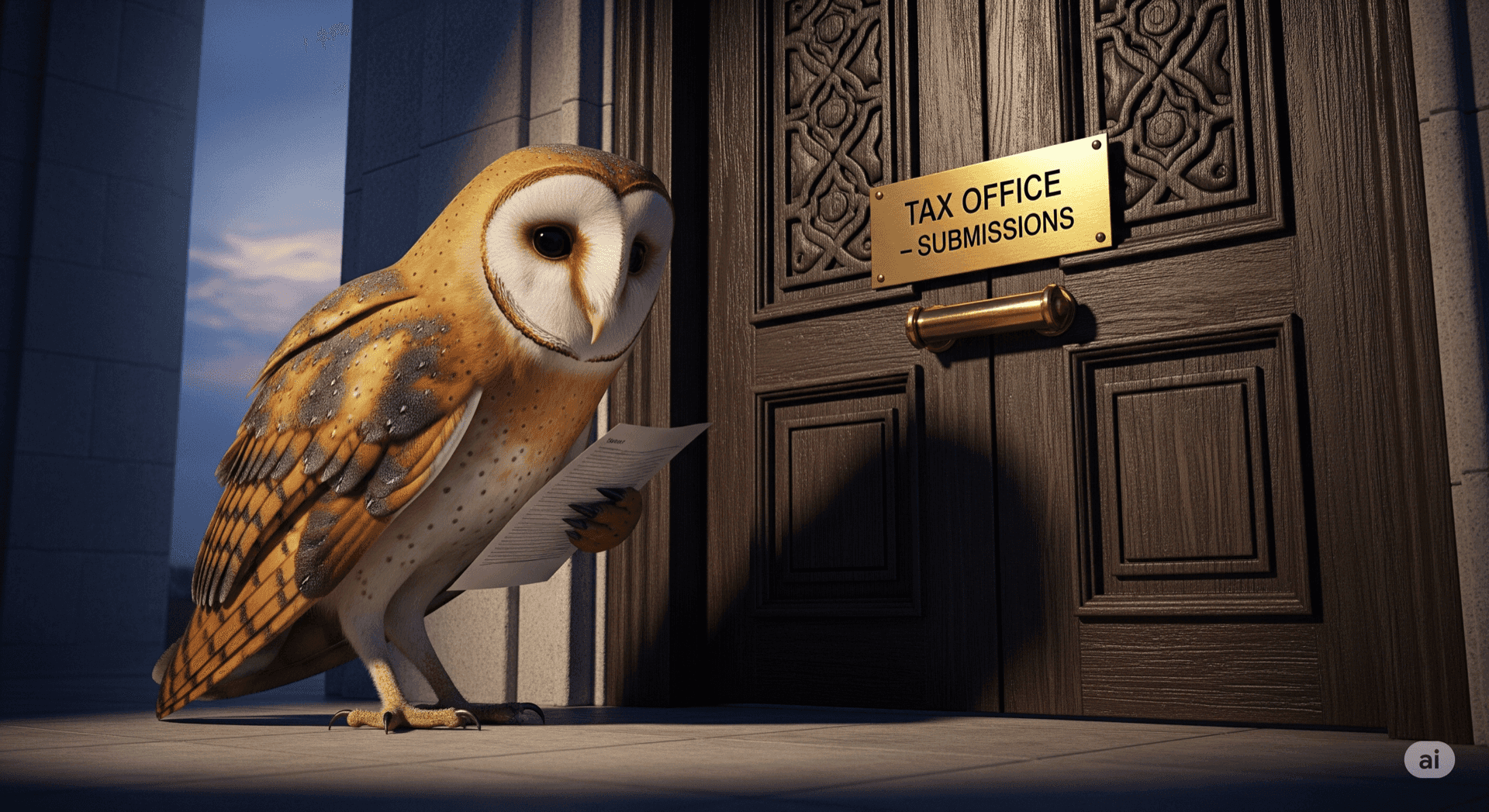
前述の通り、個人が暗号資産の評価方法に関する届出書を所轄の税務署に提出していない場合、所得税法上、自動的に「総平均法」で評価することが定められています。したがって、とくに手続きをしていなくても、総平均法で所得を計算し確定申告を行えば、税務上はまったく問題ありません。
もし「移動平均法で計算するつもりだったが、届出を忘れてしまった」という場合は、その年については総平均法で申告する義務があります。翌年以降に移動平均法へ変更したい場合は、その変更したい年の確定申告期限(通常は翌年3月15日)までに「所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書」を提出し、税務署長の承認を得る必要があります。
ビットコイン(BTC)など主要通貨の計算例₿
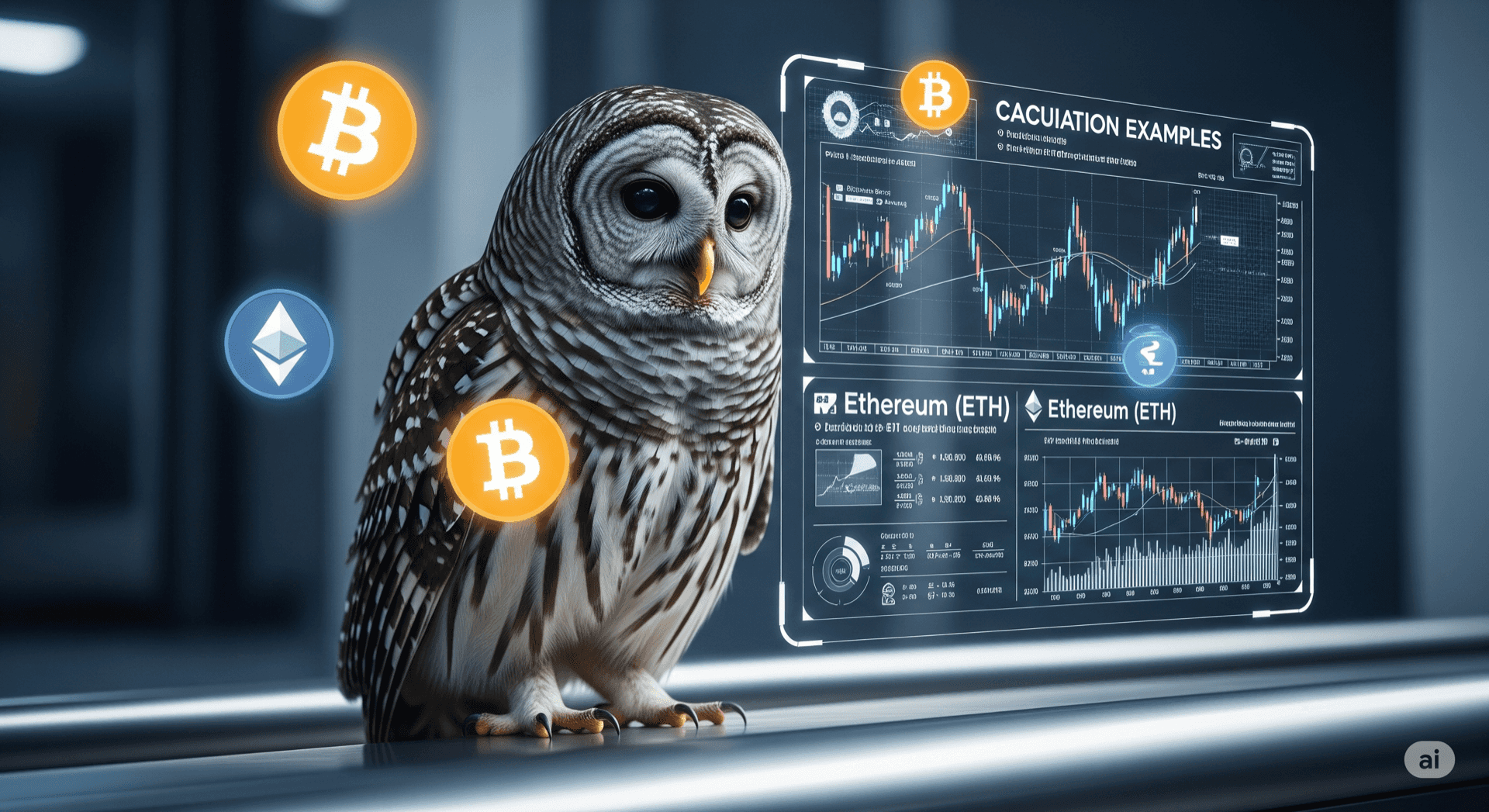
総平均法の計算方法は、ビットコイン、イーサリアム、リップルなど、どの暗号資産であってもまったく同じです。重要なのは、計算は通貨の種類ごとに行うという点です。
たとえば、ビットコインとイーサリアムの両方を取引している場合、以下の手順で計算します。
ビットコインの年間の全取引(購入・売却)を集計し、BTCの総平均単価と所得を計算します。
イーサリアムの年間の全取引(購入・売却)を別途集計し、ETHの総平均単価と所得を計算します。
確定申告書には、これら複数の暗号資産から生じた所得の合計額を雑所得として記載します。
さらに注意すべきは、複数の取引所で同じ通貨を取引している場合です。たとえば、A取引所とB取引所の両方でビットコインを購入した場合、A取引所とB取引所の購入履歴をすべて合算して、1つの平均単価を計算しなければなりません。取引所ごとに別々の平均単価を計算するのは誤りであり、税務調査で指摘される可能性があるため、厳に注意が必要です。
便利な暗号資産の税金計算ツール₿
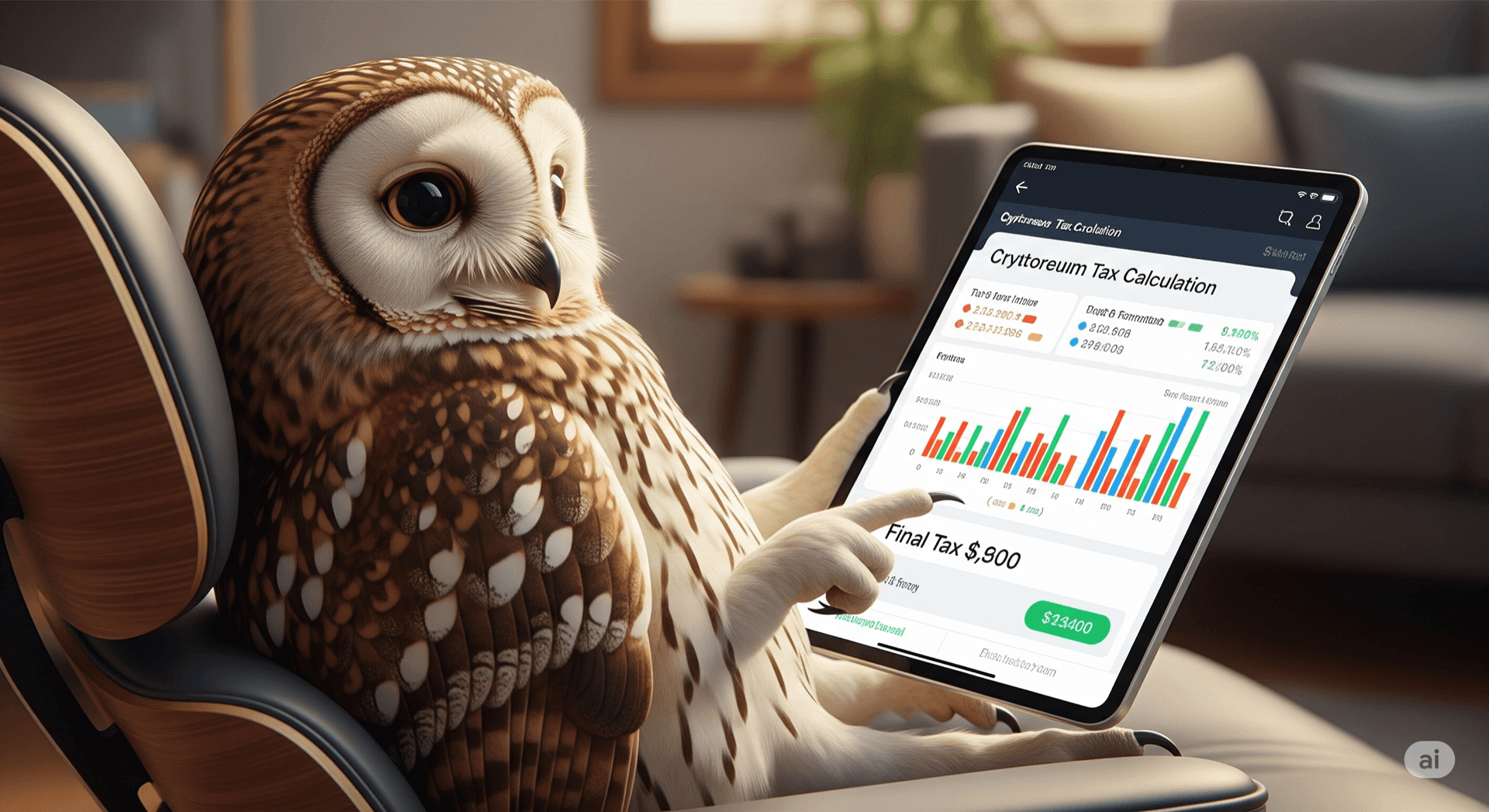
取引所が複数にまたがる、海外取引所を利用している、あるいはDeFiでの運用(ステーキング、レンディング、流動性提供)やNFTの売買など、取引が多様化・複雑化してくると、手動での損益計算は現実的ではありません。国税庁の計算書も、こうした複雑な取引には対応していません。
つまり、税法はすべての取引から生じる所得の申告を求めているにもかかわらず、国が提供する公式ツールはその計算をサポートしきれていないのです。このギャップを埋めるために、市販の暗号資産専門の損益計算ツールの利用が事実上不可欠となっています。
これらのツールは、各取引所の取引履歴データ(API連携またはCSVファイル)をアップロードするだけで、総平均法または移動平均法のいずれかを選択して、複雑な取引も含む全取引の損益を自動で計算してくれます。
表2:主要な暗号資産税金計算ツールの比較
| 特徴 | Gtax | クリプタクト | クリプトリンク |
|---|
| 株式会社Aerial Partners | 株式会社pafin | クリプトリンク株式会社 |
| 主な利用者層 | 個人から法人、税理士まで幅広く利用。税務の専門家からの信頼が厚い。 | DeFi/NFT取引を多用する個人投資家やグローバルな取引を行うユーザーに強み。 | 個人から事業者まで。不要資産の0円引き取りなどユニークなサービスも提供。 |
| 無料プランの範囲 | 年間取引100件まで。主に国内取引所のみ対応。DeFi非対応。 | 年間50件までの損益計算。海外取引所、DeFi/NFTの自動識別にも対応。 | 年間100件まで。国内取引所のみ。DeFi/NFT機能は有料。 |
| 有料プラン(個人) | 年額5,500円~。取引件数に応じた段階的料金。上位プランでDeFi対応。 | 年額6,600円~。全有料プランで強力なDeFi/NFTサポートを提供。 | 年額3,960円~。オプションプランでDeFi/NFTに対応。 |
| DeFi/NFT対応 | 有料プランで対応。主要チェーン(ETH, Polygon, BSC等)をカバー。 | 非常に強力。ウォレットアドレス連携で取引を自動識別。Uniswap v3等にも対応。 | 上位のオプションプランで対応。 |
| 差別化要因 | 税理士業界での高い実績と信頼性。 | 業界最高水準のDeFi/NFT自動化技術とグローバル対応。 | 損益計算代行サービスや資産処分サービスといった付加価値。 |
参考:
広告
暗号資産の総平均法を総括₿
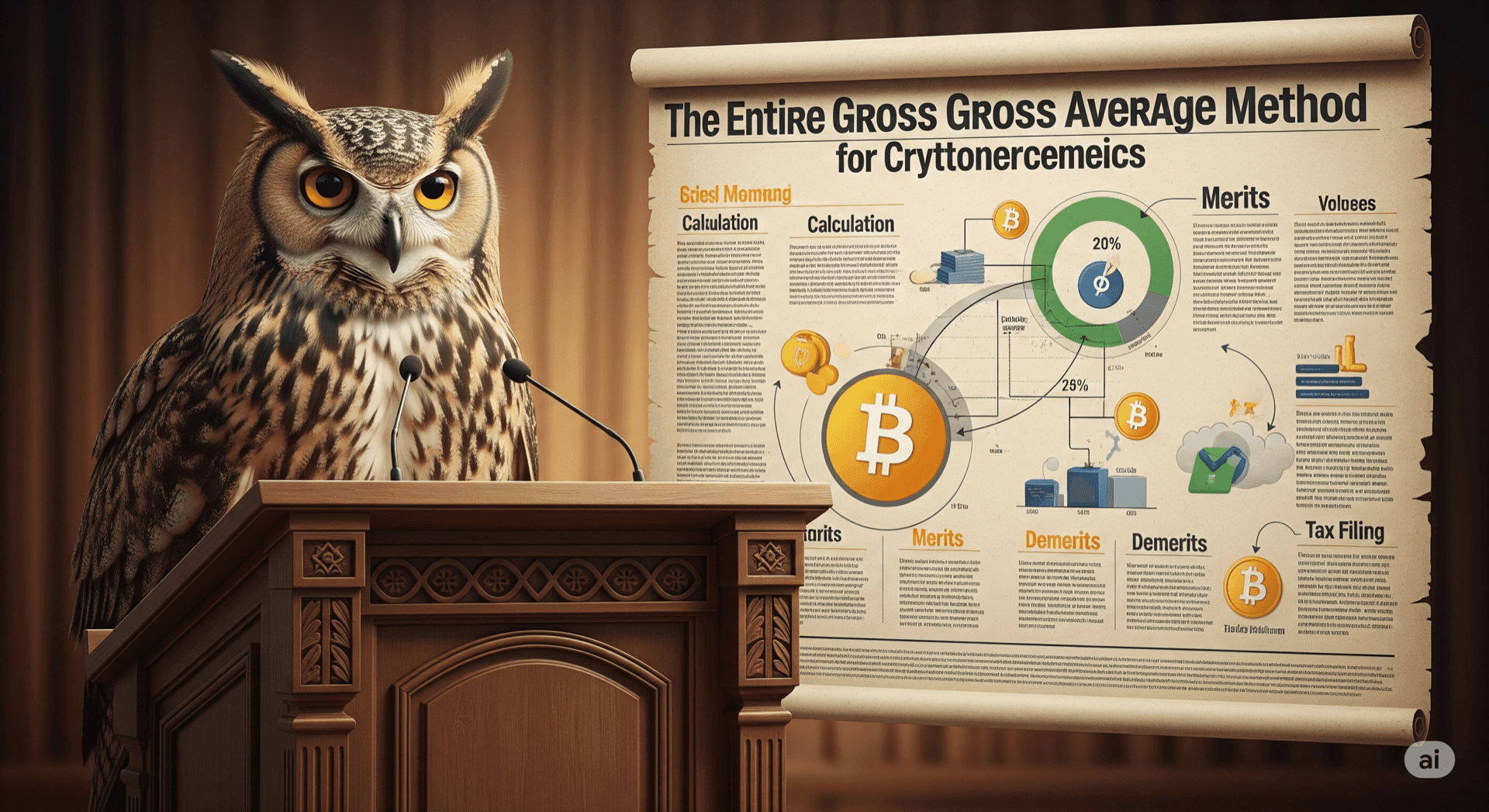
総平均法は、計算がシンプルであり、特別な届出も不要なため、多くの個人投資家、とくに取引が比較的単純な方にとっては、取り組みやすい所得計算方法です。国税庁が提供する計算書を活用すれば、国内取引所の年間取引報告書を基に、スムーズに確定申告の準備を進めることが可能です。
しかし、その簡便さの裏には、期中の損益が不透明になり、計画的な税務戦略が立てにくいという大きなデメリットが存在します。価格変動の激しい暗号資産市場において、このデメリットは無視できません。
評価方法の選択は、単なる計算手続きの問題ではなく、複数年にわたる納税額に影響を与える可能性のある戦略的な決定です。一度選択すると原則として3年間は変更できないという「3年ルール」の存在も、その重要性を高めています。このルールの根拠は所得税法施行令第119条の4にあり、恣意的な利益操作を防ぐ目的があると考えられますが、投資家にとっては大きな制約となります。
自身の取引スタイル(短期売買か長期保有か)、所得水準、将来の市場に対する見通しを総合的に勘案し、総平均法と移動平均法のどちらが自身の状況にとって最適かを慎重に判断することが求められます。そして、取引が複雑化している現代においては、正確かつ効率的な申告のために、信頼できる損益計算ツールを導入することも、賢明な投資家にとっての標準的な対応と言えるでしょう。どのような方法を選択するにせよ、すべての取引を正確に記録することが、あらゆる税務コンプライアンスの出発点であることは言うまでもありません。
参考:
広告
更新